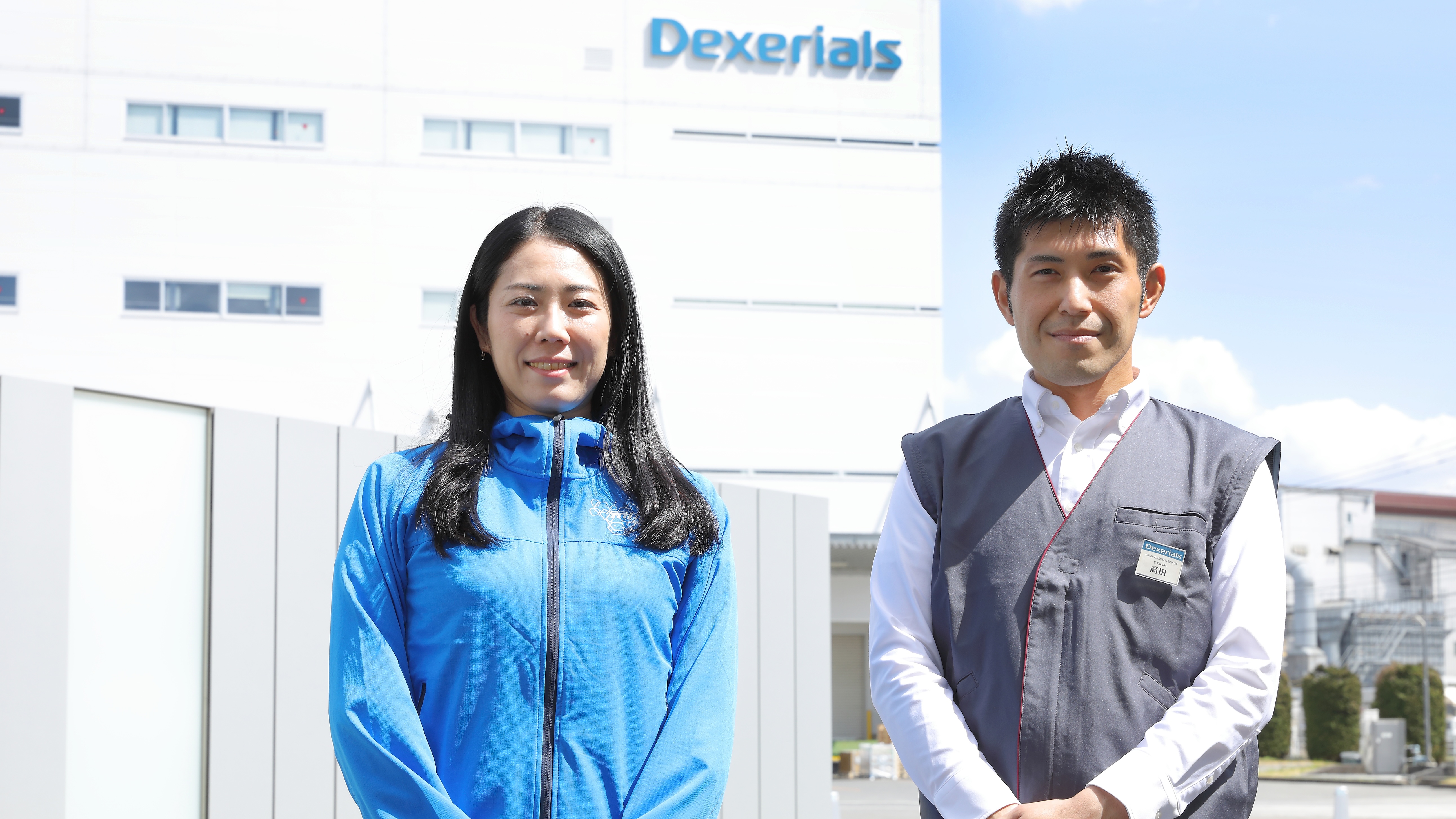半導体製造に不可欠な研磨関連資材のリーディングカンパニー、ニッタ・デュポン株式会社。顧客の技術革新を後押しする最適な研磨ソリューションを提供し、進化し続ける半導体技術の根幹を担うことで、デジタル社会の発展に貢献されています。
同社では、2023年よりマテリアルズ・インフォマティクス(以下、MI)導入の検討を開始し、2024年にmiHub®を導入していただきました。その背景と今後の展望について、技術本部 本部長 太田 慶治様、技術本部 評価技術部 部長 小川 一幸様、そしてMI推進者である技術本部 評価技術部 主務 尾関 晃様にお話を伺いました。
半導体技術の進化による高度な要求に合わせた開発の効率化が長年の課題に
まずは貴社の事業概要と主要製品のご紹介からお願いいたします
ニッタ・デュポン株式会社は、半導体デバイスやシリコンウェーハの製造に用いられる精密研磨用消耗資材を手がける専門メーカーです。中でも研磨パッドは、業界の標準仕様として非常に高いマーケットシェアを誇っています。
当社の強みは、研磨パッドと研磨剤であるスラリーの両方を自社で一貫して開発・製造できる点です。この独自の体制を基盤とすることで、お客様のニーズに合わせて両製品を最適に組み合わせた“トータルソリューションの提供”が可能となります。こうしたアプローチは、当社が業界に先駆けて確立したものです。
スラリーとはシリカなどの砥粒を含んだ液体のことで、半導体の基板であるウェーハをパッドに押さえつけながらスラリーを流し、化学的・機械的な作用を組み合わせて表面を精密に磨き上げます。当社の研磨パッドが業界標準であるからこそ、このような最適な組み合わせのご提案が可能になるのです。

MIの導入を検討したきっかけと背景をお聞かせください。
まず、MI導入の背景には、当社の製品が用いられる半導体市場からの要求が、年々高度化・複雑化していることが挙げられます。この進化を最も身近に感じられるのが、スマートフォンです。例えばスマートフォンの性能向上は、頭脳である半導体の進化によって支えられています。そして、半導体の高性能化に不可欠なのが、内部配線の微細化です。この微細化の進展に伴い、お客様が採用される材料が新しくなれば、当然、研磨の対象物も変化するため、それに対応した製品開発が必要です。
また、「製品の歩留まりを向上させたい」というお客様のご要望も、私たちが向き合うべき重要なテーマです。その実現のためには、従来は活用が難しかったウェーハ外周部までを有効活用する必要があり、結果として研磨パッドそのものの一層の進化が求められるのです。加えて、研磨時に発生する微細な傷を限りなくゼロに近づけるといった、高いレベルでの品質向上も求められています。
このような市場の要求に応えるために、ほとんどの技術者が常に複数の開発プロジェクトを抱えているのが実情です。特にこの業界の性質上、短期間での開発が求められるため、「いかにして開発を効率化するか」は長年の課題でした。
さらに、開発業務において、新入社員とベテランの間にある知識や経験の大きな差、そして、貴重な知見が言語化されないまま属人化しているという課題もありました。
もちろんDOE(実験計画法)のような統計的手法も活用していましたが、パッドとスラリーの相性や使用する装置など、無数の要因が複雑に絡み合う開発テーマでは、古典的な手法だけでは最適解を見出すのが困難なケースが非常に多くありました。その結果、個々の実験データは担当者の中に閉じてしまい、組織のナレッジに繋がらない。こうしたデータの体系的な管理も、大きな課題として捉えていました。
現場の戸惑いを乗り越えた、戦略的なMI導入
まず、尾関様がMI推進の中心を担うことになった経緯をお聞かせください。
私が所属する評価技術部は、開発部門や生産技術部門を技術面からサポートする組織です。他のメンバーが、お客様への提案に向けた実験方法の考案や製品の物理的な分析といった実務を担当する一方で、私は、数値シミュレーションのような「数値的なアプローチ」による解析を専門としていました。
しかし、業務を通じて次第に専門領域がデータ分析へと広がり、部署を横断してさまざまな相談を受ける機会が増えていきました。こうした経緯から、データ活用の可能性を探る立場としてMI推進を担うことになりました。
miHub®導入の決め手を教えてください。
第一に、「ユーザーである開発者自身が直接データを扱える」という点です。専門家と開発者の間の壁が低くなり、特に若手メンバーとの意思疎通もしやすくなることで、開発全体のコミュニケーションが格段にスムーズになると期待しました。
第二に、「データが一元管理され、ナレッジとして蓄積・再利用できる」点です。 従来のDOEでは個人のPCにデータが散在し、知見が繋がっていませんでした。誰が使っても同じロジックで最適解を導き出せる一元的な仕組みは、私たちの根本的な課題を解決する上で不可欠だと考えたのです。
最後に、複数のライセンスによってチームが並行して活用できるという実用面も組織での導入を後押しする重要な要件でした。

MI導入における苦労や乗り越えるために工夫されたことはありましたか。
MI推進者としてまず向き合うことになったのは、導入当初の現場の率直な反応でした。対象となったユーザーにとっては純粋な追加業務になることに加え、「既存のツールと何が違うのか」といった戸惑いの声もあり、必ずしも好意的に受け入れられたわけではありません。まさに、すべてが手探りの中でのスタートとなりました。
そうした状況を踏まえ、まずは導入に意欲的なメンバーと、成果の出やすいテーマを選定し、スモールグループで活用を開始しました。初年度は、具体的な成果を出すことよりも、まず「miHub®が私たちの開発において本当に有用なのか」を見極めることにしました。手応えを得られれば、その成功事例をもって徐々に社内へ展開していく。そうすれば、当初は関心の薄かったメンバーも有効性を理解し、自然と組織全体に活用が浸透していくはずだと考えたのです。
テーマ選定は、社内の各部署から、日々の開発業務における課題や改善テーマを募りました。それを尾関が中心となって、「既存のツールで対応可能か」といった観点でスクリーニングを行いました。その上で、MI-6の担当者の方にもご相談し、実現可能性を多角的に検証した上で最終的なテーマを選定し、プロジェクトを開始しました。
このように丁寧なプロセスを踏んだのは、「miHub®で成果を出せ」とトップダウンで指示するだけでは、メンバーのプレッシャーになると考えたからです。本来の目的はツールを使うこと自体ではなく、「開発したい製品をいかに効率よく開発するか」であり、ツールはそのための“選択肢の一つ”に過ぎません。ですから、初年度は「まず使ってみる」「とにかく慣れる」ことを目標とし、成果を急ぐことはしませんでした。結果として、進捗が見えやすく、メンバーが着実に手応えを感じられるテーマを選定できたことも、良かったと思います。

導入過程では、いくつかの困難にも直面しました。特に、DOEに慣れていたスラリー開発のメンバーにとっては、特定の範囲で最適解を探す「局所最適化」の思考から、より広い探索空間で最適解を探るmiHub®の「大域的な最適化」という考え方へのマインドセットが、大きなハードルでした。しかし、こうした試行錯誤も、新しいツールに慣れる過程では貴重な経験になったと捉えています。
また、当初はメンバーが個々の抱える開発テーマとツールとの相性によって、進捗に大きなばらつきが生じてしまいました。このままでは全社横断的な展開は難しいと判断し、途中で方針を修正しました。具体的には、導入過程での反省を踏まえて開発テーマを再設定し、それに合わせてメンバーの再編成を行っています。
MI専門家の伴走支援がもたらした、驚くべきチームの変化と成長
MI-6の支援は、どのように役立ちましたか。
特に、MI-6による定期的な“伴走支援”が、私たちにとって大きな助けとなりました。
初年度は、特定の担当者のテーマに関するミーティングであっても、ほぼ全ユーザーが参加し、「この結果をどう解釈すべきか」といった点を皆で学び合うという姿勢を徹底しました。そのような状況の中、MI-6の担当者さんに“伴走”していただくことで、私たちユーザーは“並走”しながら、五里霧中の状態から一歩ずつ着実に前進することができたのです。この1年間、まるでマラソンのように皆で励まし合いながら乗り越えてきたことで、チームの連帯感も格段に強まったと感じています。
MI推進者である私自身の経験としても、このサポート体制には大いに助けられました。導入当初はmiHub®の操作や見慣れないグラフの解釈に苦戦しましたが、サポートミーティングで相談するたびに、非常に親身に指導してくださいました。適切な問題設定にはある程度の経験が必要ですが、このプロセスを通じて「とにかくサイクルを回すこと」の重要性を改めて実感しましたし、使い方とテーマの親和性によってはmiHub®が非常に強力なツールになり得ると確信しています。
MI-6の担当者の方と対話を重ねる中で、ユーザーたちのツールに対する理解が格段に深まっていったのは間違いありません。プロの視点が加わることで、私たちの計画の「解像度」が上がっていきました。

導入によって、具体的にどのような成果や社内の変化がありましたか。
初年度テーマのうち、当初は困難だと予想されていたテーマで、非常に興味深い結果が得られています。これまでは担当者の経験や感覚に頼りがちだった材料開発において、25回の実験サイクルを重ねた結果、新規材料の情報を入力するだけで実用に近いレベルの有望な処方を提案できるようになりました。
担当者からの報告によれば、このプロセスによって、「開発にかかる工数が従来比で4分の1から5分の1程度に短縮された」とのことです。このように、粘り強く継続してきたテーマで、目に見える成果が生まれ始めています。
まだ活用を開始して1年数か月ほどですが、プロジェクトの確かな手応えを感じており、miHub®の活用によって、「明らかに開発が促進された」と実感できる良い事例が着実に生まれつつあります。メンバーに過度なプレッシャーをかけず、「これはあくまでも数あるツールの一つだ」と伝え続けることで、長期的な視点で取り組めるよう心がけています。
そして、非常に喜ばしい変化も生まれています。尾関が中心となり、ユーザー間で自発的な定期ミーティングが開催されるようになったのです。便利な機能や互いの工夫を共有するだけでなく、普段は開発アプローチが異なるパッドとスラリーの担当メンバーが、互いの立場や考えを深く理解し合うという、当初の期待を上回る相乗効果が生まれています。
ユーザー間の自発的な交流が、組織全体に良い影響を与えていると感じています。その象徴的な場となっているのが、4ヶ月に1回程度のペースで実施しているレビュー会です。この場では、ツールを上手く活用しているメンバーが、まだ習熟していないメンバーに対して「こうすればもっと活用できるかもしれない」と、自発的にレクチャーする光景も見られます。
こうした交流を通じて新しい開発アプローチの利点を皆で共有することで、miHub®から思わぬ提案が生まれるといった効果にも繋がっています。さらに、このような事例は、「自分たちもmiHub®を使って新しい製品を作ってみたい」という、他のメンバーへの良い刺激にもなっていくと考えています。
定期的なミーティングを通じて自然と部署横断の議論を行うようになり、その中から課題解決に繋がる思わぬアイデアが生まれることも少なくありません。こうした組織の変化と並行して、個々のマインドにも大きな変化が見られました。例えば、miHub®から予期せぬ材料の組み合わせが推奨されることで、技術者の「新しい可能性を試そう」というモチベーションを刺激しています。
そして、何より私が驚いたのがメンバーの“主体的な姿勢”です。好奇心に火がつき、「今まで使ったことのない機能にも挑戦しよう」と、自ら主成分分析のような別の統計手法を学習し、解釈を深めるメンバーも現れました。また、「これまで定性的にしか捉えていなかった情報を、いかに定量化してmiHub®に入力するか」といった工夫を自発的に始めるメンバーも現れました。こうした主体性こそが、プロジェクトを良い方向へ導く原動力だと感じています。
メンバーの成長に伴い、私自身の役割も変化しました。 導入当初は、私が操作方法やアウトプットの解釈を指導する役割でしたが、1年が経過した今、各メンバーが自律的にmiHub®を使いこなせるようになっています。定期ミーティングも、今では特定のツールに限定せず、業務全体の課題をオープンに議論できる場になっており、チームとしての確かな成長を実感しています。

単にツールに依存するのではなく、miHub®を「有用なツールの一つ」として客観的に位置づけ、そこから得られるデータに基づくヒントと、技術者自身が持つ本来の知見や考察とを、主体的に融合させながら開発を進める姿勢が明確に見て取れるようになりましたね。
データに基づき迅速に試して、より本質的な開発へと繋げていく
最後に、今後の展望をお願いします。
大きく2つの目標を掲げています。1つは、ユーザー層をさらに拡大し、個人の経験や勘だけに依存するのではなく、若手からベテランまでがデータに基づいて「論理的に議論できる開発文化を醸成する」こと。もう1つは、得られたデータを一過性のものとせず、他のプロジェクトでも横断的に再活用できる、「全社的なナレッジデータベースを構築する」ことです。
とはいえ、その実現は決して簡単なことではなく、実際は非常に泥臭い作業の連続です。日々の業務にmiHub®をいかにして最適に組み込んでいくか、インプットとアウトプットの両面で今も試行錯誤を重ねています。それでも、着実に一歩ずつ前進しているという実感はあります。
これまでは、良くも悪くも個人の経験値に頼る開発スタイルが主流であり、社内のデータベース等が十分に活用されているとは言えない状況でした。今回のMI活用の取り組みは、そうした属人化した開発スタイルから脱却し、蓄積されたデータに基づいて開発を推進するという、新たなステージへの重要な第一歩だと捉えています。
この一歩をきっかけに、私たちが最終的に目指すのは、「テーマに応じて最適なツールを主体的に選択できる」開発文化を社内に根付かせることです。miHub®が「数ある効率化手段の中の、特に有用な選択肢の一つ」として、開発者一人ひとりにしっかりと認知される状態を築いていきたいと考えています。
今回の取り組みが良い方向へ進んでいる要因の一つは、プロジェクトの進め方そのものの柔軟性にあると考えています。過去の経験上、計画を厳密に固定化したプロジェクトほど、不測の事態に直面した際に軌道修正ができず、頓挫することがありました。その反省を活かし、状況に応じて柔軟な方針転換をしてきたことが、今回の結果に繋がったのではないでしょうか。
今回得られた最も重要な収穫は、メンバーが「サイクルを回すこと」の重要性を深く、体感的に理解してくれた点にあります。これまでは少数の実験に時間をかけ、深く議論する傾向がありましたが、今後はmiHub®の利用有無にかかわらず、「とにかくサイクルタイムを短縮し、多くのデータに基づいて迅速により良い製品を生み出していく」というマインドセットこそが、チーム、ひいては会社全体の文化として浸透することが最大の成果になると考えています。
太田様、小川様、尾関様ありがとうございました!
※掲載内容は取材当時(2025/8/1)のものです。
SaaS型実験計画プラットフォームmiHub®の詳細は以下から無料でダウンロードが可能です。
miHub®の資料請求はこちら
その他のMIに関するご相談については、下記アドレスまでお気軽にお申し付けください。
MI-6株式会社 事業開発部 bd@mi-6.co.jp