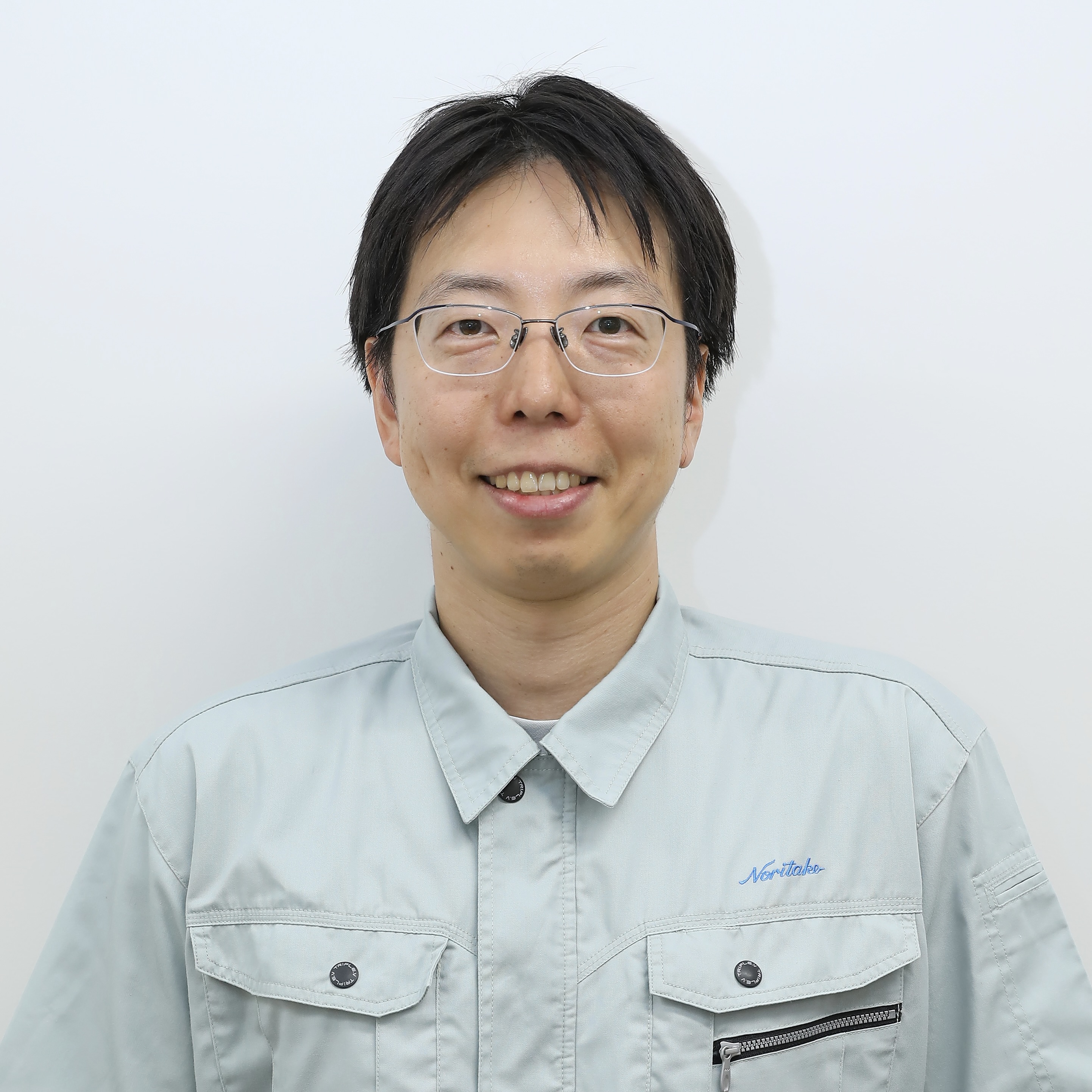創立120年以上の歴史を有し、セラミックメーカーとして世界に名を馳せるノリタケ株式会社。‟事業を通じて社会に貢献する”という理念のもと、長年培ってきた独自の技術力を基盤に、洋食器をはじめ先端技術産業や基幹産業に至る幅広い分野に技術と製品を提供しています。同社では2020年頃より、マテリアルズ・インフォマティクス(以下MI)導入の検討を開始し、2023年にmiHub®を導入していただきました。その背景と今後の展望について、研究開発センターの山田祐貴様、工業機材事業本部の森田雅也様にお話を伺いました。
高度化・複雑化する顧客ニーズに応える新材料開発が求められる
まずは、貴社の事業概要や事業部のご紹介からお願いいたします。
ノリタケの歴史は食器製造から始まり、そこで培った技術を応用・展開し事業の多角化をしてきました。例えば、創立当時、食器製造には砥石、高品質な材料、焼成窯が不可欠でした。これらを内製する過程で、工業機材、セラミック・マテリアル、エンジニアリングといった新たな事業が生まれました。祖業である食器事業と合わせ、現在ではこの4つの事業を展開しています。
長年の技術蓄積してきたセラミックスの技術と、材料から装置まで一貫して手がける事業の幅広さこそが、時代の変化に対応できるセラミックメーカーとしての当社の強みです。自動車や鉄鋼関連が主な対象領域でしたが、時代のニーズに合わせた事業展開を目指し、現在は環境、エレクトロニクス、ウェルビーイングの3分野を新たな成長領域と定めています。
私の在籍する研究開発センターは、特定の事業に属さない組織として、基盤技術をさらに進化させ、新技術・新製品の創出を担っています。中でも私がリーダーを務めるチームはMIを積極的に取り入れており、MI-6との連携では中心的な立場で各事業や社外との調整役を務めています。私自身はガラス材の開発を担当しておりますが、当社のガラス技術は食器の釉薬を起点に、砥石や歯科材料など、さまざまな製品の性能を左右するキーマテリアルとして活用してきました。表に出ることは少ない黒子のような存在ですが、製品の差別化を支える非常に重要な材料です。
私は工業機材事業本部に所属しており、DX推進チームのチームリーダーを務めています。私たちの事業は砥石、つまり削る・磨く技術において特定分野に特化するのではなく、あらゆる領域をカバーする幅広さと、長い歴史に裏打ちされたデータや知見の深さを強みとしています。
私のチームの役割は、この蓄積された強みを活かし、事業活動を加速させることです。事業全体のDX課題の解決や基盤整備を通じて、変化に対応し事業の発展を支えています。
ガラス・砥石材料の開発トレンドやMI導入を検討し始めた背景をお聞かせください。
近年、EVや電動化の急速な進展により、お客様から求められる機能は急速に高度化・複雑化しています。私が開発している特殊なガラス接合材も、そうしたニーズに応えるための一例です。
EVの部品のように大電流が流れ、極めて高温になる用途では、接合材にも高い耐熱性が不可欠です。しかし、一般的な樹脂系接合材は、熱に晒されると劣化してしまいます。そこで、無機材料であるガラスに置き換えることで、この高温での接合という課題を解決することができます。
一方で、より幅広い用途に対応するため、従来のガラス接合材よりも低温(約300~350℃)での接合を可能にすることが求められています。このような開発では、従来にない新しい特性の材料の開発が不可欠であり、挑戦すべき開発領域そのものが広がり続けているのです。
砥石の分野でも同様の課題に直面しています。物を削って滑らかにすることが砥石の役割ですが、近年のトレンドは、従来以上の高精度な仕上げです。特に、半導体関連の研削・研磨加工の市場は拡大しておりますが、微細で硬い材料を扱うため、求められる精度は金属加工とはまったく異なり、開発の難易度は格段に高くなっています。
それに加え、市場からは開発スピードの向上も強く求められ、「開発リソースをどう捻出するか」という、課題も生まれていたのです。こうした2つの課題に対し、「一人の開発者の長年の経験と勘に頼る従来の手法では、もはや応えきれない」という危機感がありました。「高品質な製品をより早く開発するためには、MIのような新しい開発手法が不可欠である」この認識こそが、MI導入検討のきっかけです。

操作性の良さと手厚いサポート体制への信頼から導入を決定
miHub®を導入された経緯や、選定の決め手を教えてください。
私自身が参加する前の2020年から2021年頃、社内でMI導入の検討が始まりました。まず、研究開発センターに調査グループが発足し、複数のサービスを試す中でMI-6を見つけ、コンタクトを取ったと聞いています。
最終的には、先行していたメンバーの意見とMI-6担当者の方の説明を総合的に判断し、「ノリタケに最も適している」との見解で導入が決定しました。MIという未知の領域に挑む不安を、事前の丁寧な説明で払拭していただけたこと、そして手厚いサポート体制への信頼も大きな決め手になりました。
MIは実験を繰り返しながら答えに近づく性質上、専門家だけでなく、開発者自身が直接ツールを使いこなせることが重要だと考えていました。そのため、プログラミングの知識がなくても直感的に使える‟操作性の良さ”も検討基準の一つです。その点で、Webサービス上で操作しやすいmiHub®は、まさに私たちが求めていたものでした。
その決断の背景には、お二人のこれまでのご経験や課題意識も影響したのでしょうか?
はい。私自身、10年以上にわたるガラス材料開発の中で、開発期間の短縮や知見の属人化は長年の課題で、MIに可能性を感じていました。ただ、少し語弊があるかもしれませんが、私自身は実験・経験を重視するタイプで、データ解析には正直なところ苦手意識があったのです。そのため、当初は「何か新しいことをやっているな」と遠巻きに見ているだけで、積極的に関与していませんでした。ただ、経験だけでは開発が頭打ちになるという危機感は高まり、新たな技術の必要性を痛感している状況でもありました。
山田とはまた別の動きになりますが、私は、MIを開発に取り入れたいと考え、独学で学び始めていました。当時は本に載っているコードを動かすような形から入りましたが、基本的なプログラム知識があればスタートは切れるという感触だったので、内製プログラムを自作し試した経験から2つのことを強く感じました。
1つは標準的なデータベースが確立されている材料におけるMIの大きな将来性。もう1つが、MIを社内で推進していく難しさです。
AIに解析させるデータが不足していると初期段階での推進力が弱まり、特に実験担当者の「AIなら答えを出してくれるはず」という高い期待に応えられないと、「これは使えない」と判断されかねません。このギャップを埋めることが、MIを社内に普及させるための大きな課題だと痛感しました。そうした課題意識の中で出会ったのが、開発者自身が直接使えるmiHub®でした。独学の難しさを感じていた私にとって、”直感的にスムーズに利用できる”というコンセプトが自身の課題意識と合致しました。
それぞれが課題感を抱える中、以前から交流があった森田から「一緒に挑戦してみないか」と声をかけてもらったのがきっかけです。私一人ではデータ解析のイメージが湧きませんでしたが、彼のMIに対する知見と、私の持つ材料の知見やデータを組み合わせれば、何か面白いことができるかもしれないと考えました。
加えて、「誰でも直感的に活用できるツールなら、データ解析に苦手意識がある自分でも挑戦できるかもしれない」と思えたことも、参加を決心する上で大きな後押しとなりました。そして、「まずはMI-6から詳しい話を聞こう」と、森田と相談しました。
当時はまず自分の事業内でMIを広めたいと考えていましたが、一人での推進には限界を感じていました。そうした中でmiHub®の活用を模索していたところ、思いに共感してくれる心強い味方が現れてくれたという感覚です。
MI活用で開発期間を半分以下に短縮、諦めかけた目標を達成
どのようにMIの取り組みを進められたのでしょうか。
ガラス材のテーマでは、新材料の創出や開発期間の短縮に期待はありましたが、最初からハードルを上げすぎず、「まずはMIの効果を検証できれば良い」という気持ちで臨みました。
実は、森田から聞いて「ガラスとMIは相性が良いだろう」という仮説を持っていました。ちょうどそのとき、私たちが手がけていた低温で使えるガラス接合材の開発が行き詰まり、正直なところ諦めかけていたのです。もともと500℃程度だった接合温度を、さまざまな試作を経て400℃まで下げることには成功したものの、目標温度はさらに低く、手詰まりの状態でした。
そこで、「何か面白いことが起きるかもしれない」という期待から、このテーマでMIを試すことにしました。結果は驚くべきもので、ごく初期の試行で目標を達成できたのです。私自身も半信半疑でしたから、ただただ「これはすごい」と純粋に驚き、一緒に開発を進めていた後輩に思わず「すごいじゃないか」と口にしたのを覚えています。
上司に報告し、ただの偶然ではなく、特性の再現性があるかの検証も慎重に行いましたが、結果は本物でした。具体的には、従来1年かけても達成できなかった目標を、約半年で達成できました。これは、開発期間を半分以下に短縮できたことになります。
その劇的な成果は、具体的に何がもたらしたとお考えですか?
この成功の礎には、2つの要素があったと考えています。1つはノリタケが長年蓄積してきた質の良い社内データ、もう1つは適切な解析条件の設定です。当社は祖業の食器を始め、様々な製品にガラスを使用しており、ガラスに関するデータベースは社内にしっかりと蓄積されていました。ただ、それをうまく活用しきれていなかったのです。MI-6からのアドバイスを受けながら、技術者の知見を活かした適切な解析条件を設定することで、MIという手法が、眠っていた潜在的な価値を引き出してくれたのだと実感しています。
この成功体験によって、私自身のMIへの不安感は完全に払拭されました。そして、これは嬉しい副産物でしたが、具体的な成果が他の開発メンバーの「自分も挑戦してみよう」という意欲に火をつけ、"MIが人を育てる”ことにも繋がると実感しました。
私自身、これまでのMI活用の経験から、「成果を出すには一定の試行錯誤が不可欠である」と実感してきました。そのため、MIを活用しながら試行錯誤を重ねていくことこそが、取り組みにおける重要な要素だと捉えています。
しかし今回の取り組みでは、その前提が良い意味で覆されました。まだ試行錯誤の初期段階であったにもかかわらず、予想を上回るほど明確な成果が見え始めたのです。MIの持つ可能性を改めて実感するとともに、着実に成果へとつながる道筋が見えたことに、大きな手応えを感じています。
初回の成功は、あくまで暫定目標をクリアした段階ですが、そのインパクトは絶大でした。そこからは目標を再設定し商品化を見据えた本格的なMIのサイクルを回し始めています。
※関連ニュースリリース:https://www.noritake.co.jp/news/detail/620/

社内での実績構築と成果の共有で、MI活用の組織的な拡大へ繋げる
最後に、今後の展望とMI-6への期待をお聞かせください。
各事業・部門でMIによる具体的な成功事例を一つひとつ積み上げていくことが、現在のフェーズだと捉えています。それぞれの課題に対しMIを活用できる場面を探し、技術サポートを通じて着実に実績を構築する。そして、その成功事例を社内に積極的に発信していく。このような活動の成果として、部門間のナレッジ共有はすでに始まっています。キーパーソンがMIの知見を深めることで、MIの解析結果をベースに意思決定を行う事例も出てきました。この良い流れを、今後さらに加速させていきたいですね。
山田の話にも繋がりますが、私はMIに関しては、「専門家だけでなく、実務者が使いこなして初めて意味がある」と基本的に考えています。MIを広く普及させる上では、ノーコードかつWeb上で利用できるツールが導入のハードルを大きく下げてくれます。miHub®は、まさにその強みを持つツールだと認識しています。
実際に、誰もがアクセスしやすいmiHub®が、一つのきっかけとなりました。これを起点に、私の部署でも「データをどう活用できる形で蓄積していくか」という議論が活発化し、今では“使える形でデータを貯める”という文化が着実に根付きつつあります。
MIの社内展開は、会社の差別化を推進する上で極めて重要な取り組みです。ただ忘れてはならないのは、MIはあくまで有効なツールであり、私たちの目的は「社会に役立つ新しい製品や技術で利益に繋げること」です。社内にはまだ懐疑的な声や「MIだけで完結する」といった誤解もあるため、粘り強く対話していく必要があります。伝えるべきは、MIは既存の技術や経験を不要にするのではなく、むしろ「両者を組み合わせることで真価を発揮する」という事実です。
まさに私自身の経験がそれを物語っています。MIで開発した新しいガラス材を、その後、既存の技術でうまく使いこなすことで、MIだけでは見えなかった面白い特性が見えてくることがあるのです。
つまりMIは、いわば“金の鉱脈”を見つけるための強力なツールです。そこから先は、私たちが培ってきた技術や知見で深く掘り下げていくことで、初めて本当の価値が実感できます。この考え方を軸に、MIに固執しすぎることなく既存の技術と上手く融合させながら、全社的に付加価値の高いものを生み出していきたいですね。
AI関連技術は凄まじいスピードで進化しているので、専門家をはじめとする情報を積極的にキャッチアップする人と、そうではない人との知識のギャップは加速度的に広がっていくと考えています。この技術進化の流れに乗り遅れることは企業の競争力低下に直結するため、そのギャップを埋めるパートナーとして、MI-6には今後も私たちと伴走し続けていただきたいです。
特に、担当者の方々が化学メーカーのご経験をお持ちで、私たちと同じ“ユーザー目線”で課題感を深く共有してくださる点は、非常に心強いです。MIは、本を読めば独学でも始められますが、実際に成果を出すのは非常に難しい。その実践の難しさを、MI-6の皆さんはご自身の課題として深く理解し、共感してくださっていると感じます。
実際に活用を続けてみて、担当者がノーコードで解析できる点、そして私たちのスキルレベルに合わせてサポートしていただける点が、ノリタケに非常によく合っていると実感しています。
また、MIは「失敗は成功のもと」を体現する技術だと感じています。失敗データも価値ある情報として活用できる、そして「まずは進めてみよう」という試行錯誤が推奨される。この明快さが研究者のモチベーション向上に繋がり、“働きがい改革”にも通じるのではないでしょうか。そのため経営層にも、人材育成という観点で積極的にサポートしてもらいたいと考えています。
そして何より、ノリタケの120年以上の長い歴史の中で蓄積された独自の技術やデータと、MIやDXという新しい取り組みを連携させることで、当社が注力する環境・エレクトロニクス・ウェルビーイングの各分野で、製品の一層の価値向上を目指していきます。そのためにも、MI-6には今後とも長期的な視点でサポートいただけると大変心強いです。

山田様、森田様ありがとうございました!
※掲載内容は取材当時(2025/8/28)のものです。
SaaS型実験計画プラットフォームmiHub®の詳細は以下から無料でダウンロードが可能です。
miHub®の資料請求はこちら
その他のMIに関するご相談については、下記アドレスまでお気軽にお申し付けください。
MI-6株式会社 事業開発部 bd@mi-6.co.jp