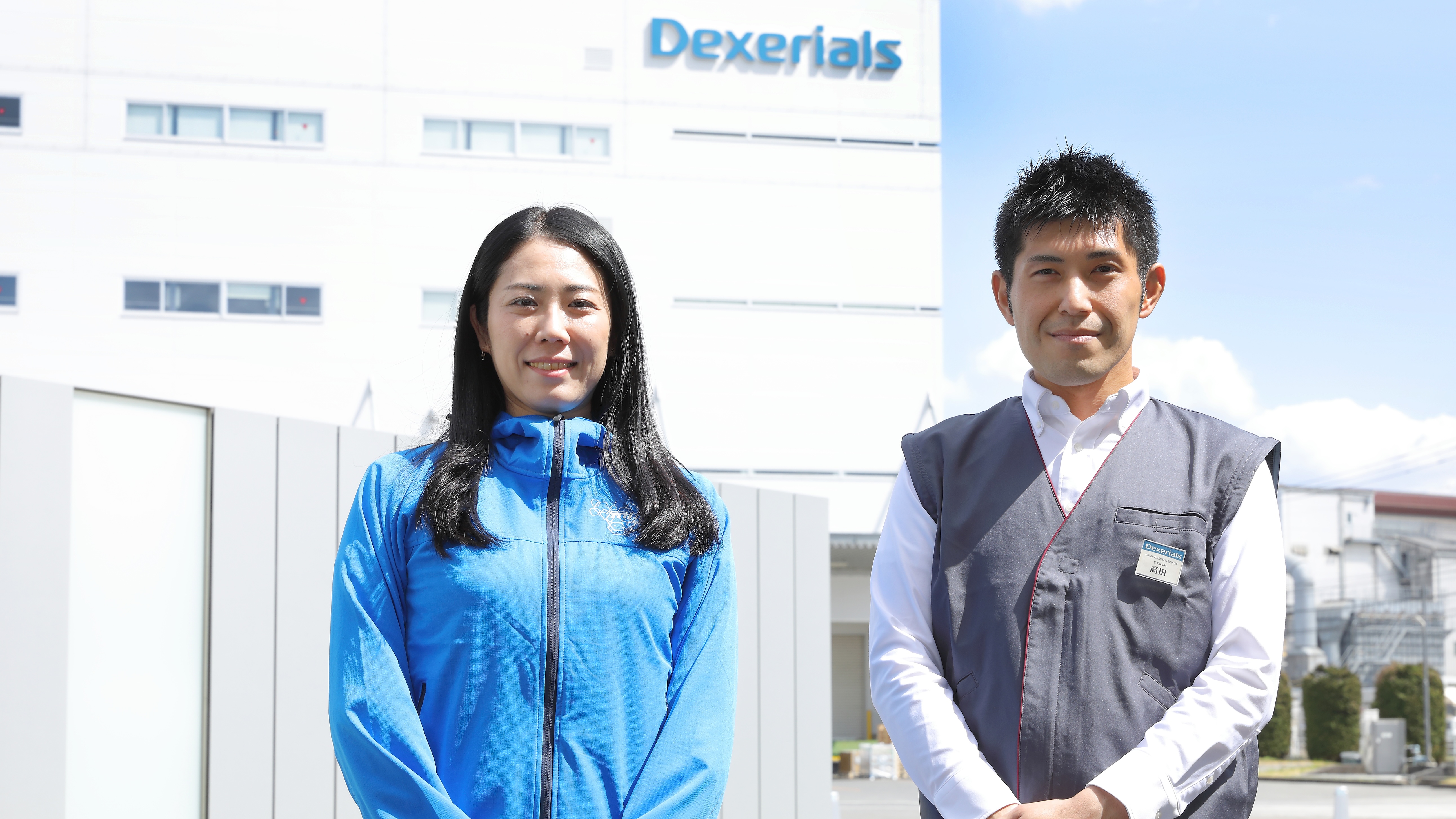世界トップクラスの自動車用自動変速機専門メーカーとして、進化を続けるジヤトコ株式会社。トップシェアを誇るCVT(無段変速機)をはじめ、50年以上培ってきた技術力とノウハウを活かした高品質なトランスミッションを供給し、世の中のモビリティ社会を支えています。同社の部品システム開発部では、2020年頃よりマテリアルズ・インフォマティクス(以下MI)導入の検討を開始。2022年にHands-on MI®を導入いただきました。その背景と今後の展望について、部品システム開発部の水野 朗様にお話を伺いました。
競争と変化の激しい自動車業界のニーズに応える必要性に迫られる
まずは貴社の事業概要と部品開発部のご紹介からお願いいたします。
ジヤトコ株式会社は自動車用自動変速機や電動パワートレインおよび部品の開発・製造・販売を手がける専門メーカーです。コア技術である変速制御技術を基盤に、燃費向上、走行性能向上、環境負荷低減を実現する製品を開発し、世界中の自動車メーカーに最適なトランスミッションソリューションを提供しています。
私が所属している部品システム開発部は、主にハードウェア部品の設計・開発を担う部署です。従来はAT/CVTを主軸としていましたが、近年はその他の領域においても先行開発を推進しています。
MIの導入を検討したきっかけと背景をお聞かせください。
近年、ガソリン車から電気自動車への移行が加速する中、当社に求められる技術も従来とは大きく変化していると認識しています。軽量化・小型化は従来のトランスミッションにおいても重要でしたが、その要求はさらに高まっている上、開発スピードの向上も求められています。
特に中国の新興メーカーの開発期間短縮が顕著なため、開発期間における競争力強化が課題です。また、ビジネスチャンス獲得のための開発プロセス変革の必要性も避けては通れません。このような社会的背景の中で、MIやAI、DXといった先端技術を積極的に導入して開発期間の短縮とさらなる品質向上を実現したいと考えていました。そんな折、展示会に参加した社員がMI-6を知ったことが、導入を検討するきっかけとなりました。
成果を得るために原理原則に基づきOne Teamで課題と対峙
データサイエンティストが伴走するHands-on MI®を選定された理由を教えてください。
他社と比較検討する中で、MIに対する考え方や技術力の高さ、そして皆さんの熱意を強く感じ、「一緒に課題解決に取り組みたい」という気持ちが芽生えたからです。
また、従来の手法では定量化が難しかった課題を解決したいという思いもありました。
Hands-on MI®での具体的な取り組み内容について教えてください。
社内はもちろん業界全体でも難題とされる「鋼の結晶粒径の異常成長」というテーマを選定しました。この現象が高強度部品で発生すると強度が低下してしまうため、当社でも防止策を講じて部品を製造しています。
MI導入前は、原理原則に基づいた不具合発生の再現実験や、品質工学を活用した取り組みを行ってきました。しかし、従来の手法では膨大な時間を要することに加え、複数の要因が複雑に絡み合う現象では、定量的な影響度の把握が困難でした。
MI導入の過程で苦労されたことはありましたか。
プロジェクト開始当初の解析結果は、「十分な説得力がある精度」とは言い難い状態で、精度向上の余地があると感じていました。しかし、MI-6の方から「一度で良好な結果を得ることは難しいですが、いずれ必ず新しい示唆に繋がる結果が得られます」と聞いていたので、一喜一憂することはありませんでした。
また、お互いの領域の理解を深めるための対話や議論を重ねることで、結果が改善され、より良い開発方向へと導かれていきました。その過程においては、One Teamとして共に取り組んでいく姿勢が重要だと感じました 。
両者の視点から多角的に検証を進め、知見を深めていくという流れなのですね。
そうですね。例えば、原理原則に関する部分は主に当社で過去の知見を基に検証を進めているので、一定のデータ収集は可能ですが、類似データが多数発生してしまう傾向があります。MI-6の方からは、データ解析の観点から、類似データの選択や、異なる視点でのデータ取得について、アドバイスを頂きました。
また、プロジェクトを進める中で、MI-6からは従来とは異なる方向性の新たな解析手法も提案してもらいました。この手法は、専門的な知見を持つMI-6だからこそ実現できたものだと思っています。結果として、その手法がうまく適合し、想定以上の定量化が可能になりました。
これにより、今後の部品開発において、材料や工法の選定にフィードバックできる手法が得られました。この成果は、上層部からも高く評価されており、今後、学会での対外発表を予定しています(自動車技術会 2025年春季大会)。

MIでの成功体験が社内に新しい風を吹かせ、可能性を広げる
Hands-on MI®の導入による成果や、社内の変化として実感されるものがあれば教えてください。
当初は「MIを活用しているらしい」「何やら難易度の高いことに取り組んでいるようだ」といった反応が大半でした。
しかし、実際に「具体的にこのような成果を達成できた」という結果が出てくると、「素晴らしい」という評価の声があがるようになり、さらに「このようなことは実現可能でしょうか」といった新たな提案や要望をもらう機会も増え始めました。
現在は、MIを研究開発で活用していくため必要な視点が得られたと実感しており、日々の開発業務をより原理・原則に基づいた丁寧かつ徹底的に実施することを重点に置くようになりました。それにより、MIにて定量解析が可能になったことで、仕事の価値を上げられる『勝利の方程式』を得たと感じています。
プロジェクトを進める中でのMI-6の支援を、どのようにご評価いただいていますか。
新しいご提案をいただけることはもちろんのこと、こちらの疑問や質問に対しても丁寧に回答してもらえるため、強い信頼を感じています。
プロジェクト初期は、私自身の知識不足もあり、打ち合わせの際には話を聞くことが中心になることが多くありました。しかし、次第に専門用語や概念を理解できるようになり、新しい手法を提案いただいた際には、その価値を実感するようになりました。
また、解析後には毎回非常に詳細な説明をしていただけるのが大変ありがたく思っています。このようなサポートがなければ、例えば「なぜその手法を用いたのか」と上司や関係者に問われた際、返答に窮してしまった可能性があります。なにより、自身でもしっかりと内容を理解し、知識を習得できているのは、支援のおかげだと感じています。
ユーザーに寄り添う理解者を得てさらなる活用を模索
最後に、今後の展望とその中でMI-6に期待されることがあればお聞かせください。
これまでに2つのテーマをMI-6とともに進める中で、プロジェクトの進め方のコツを掴めてきたように感じています。そこで、今後は視野をさらに広げ、これまでのテーマとは異なる切り口を持つ他の開発案件への適用の可能性についても検討を進めています。MIを活用すればすべての課題が解決できるわけではありませんが、原理原則に基づいた適切なデータ取得を行うことで、MIによる高度な解析が可能になると考えています。
以前のテーマでは、成果を確認できるまでに約半年かかりましたが、自社内のみで進めていた場合、さらに多くの時間を要していたと思います。検討初期は、専門家のサポートを受けながらMIの知識や技術を習得し、社内で活用できるスキルとして定着させていくことが重要だと実感しています。
MI-6には、パートナーとして期待を超える役割を果たしていただき感謝しています。直近のプロジェクトを含め、より良い形になるように最後まで一緒に作り上げていければと思っています。

水野様ありがとうございました!
※掲載内容は取材当時(2025/1/21)のものです。
MIに関するご相談については、下記アドレスまでお気軽にお申し付けください。
MI-6株式会社 事業開発部 bd@mi-6.co.jp