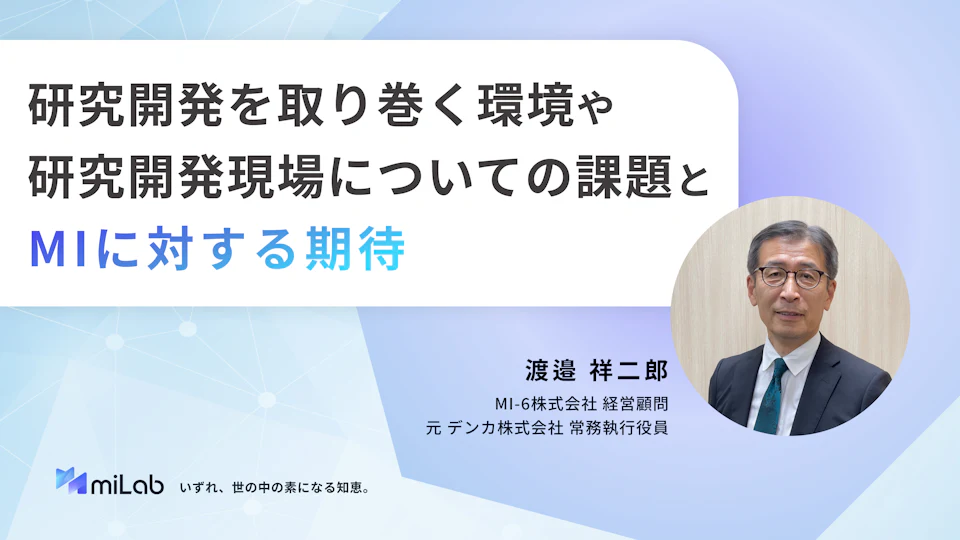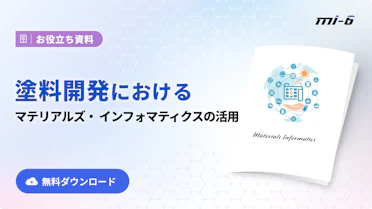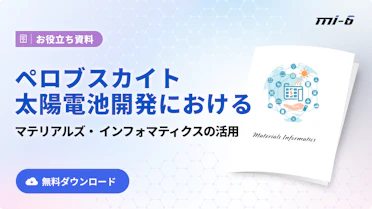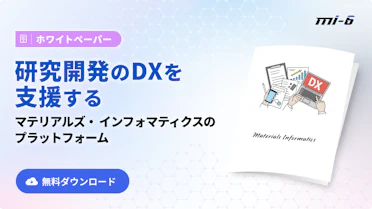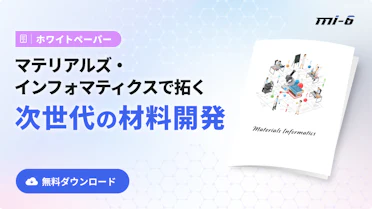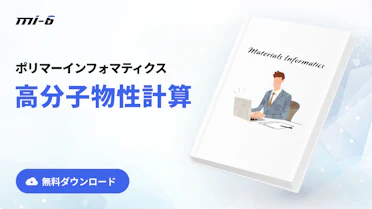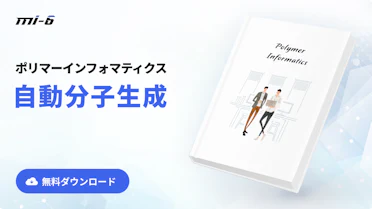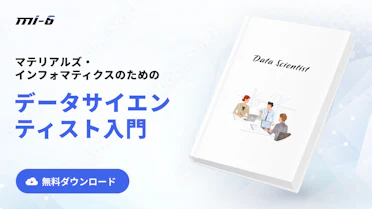はじめに
製造企業における研究開発活動は企業の成長に不可欠な源泉です。近年、研究開発環境の変化に伴い、これまでのように自社主体での研究開発による成果を出し続けることが厳しい環境になってきています。
企業活動の成果である新事業・新製品創出において、優位なポジションを有する多くの日本企業がこれまで同様なポジションを永続し、更に拡大していく為には、研究開発力を飛躍的に高める必要があります。研究開発でのイノベーションが必要な時期にあると言ってもよいでしょう。

研究開発における環境変化とイノベーションの潮流
研究開発を取り巻く社会背景の変化と厳しさを増す開発環境
世界情勢の変化
近年の世界情勢は複雑化と共にその変化が一層スピーディになり、将来を予測し、バックキャストして研究開発を開始することの不確実さが増しています。素材産業では事業化までの研究開発期間がこれまで数年から10年程度かかっていましたが、このような社会・市場の変化に呼応する為に迅速な研究開発が求められています。
健全性の担保
企業経営の健全性を担保すべく、コーポレートガバナンスとしてのESG経営をはじめとするガバナンスの強化が一層求められる時代です。従業員すべてがガバナンス策を身につけることが必須です。研究者自身も企業の一員としてESG経営に基づく企業活動に参加しなければなりません。また、健全な労働環境作りも重要であり、適切な労働時間の実現、健全な上下関係の維持といった労働環境(研究環境)作りも重要になってきています。もはや一昔前のように会社生活の中で研究に没頭する時代は日本では終わりを迎えていると言っても良いのかもしれません。
日本企業の競争力低下と研究開発環境の激化1)
1989年のバブル絶頂期、時価総額世界トップ30に占める日本企業は21社でした。2024年ではゼロ(アジア勢では台湾TSMC、韓国Samsung、中国Tencent、Kweichowの5社)であり、日本企業の国際競争力が相対的に低下していることは皆さんご認識の通りでしょう。
その中で、研究開発力も厳しい環境に直面しています。主要国の企業支出研究費(’21年)は米国が56兆円、中国46兆円、日本14兆円2)であり、特に中国を拠点とする企業の研究開発力の台頭は著しいものがあります。
中国における研究開発概況3)
世界の研究開発拠点としての中国の役割はこれまで拡大を続けてきました。中国に研究開発拠点を有する外資企業は2012年から21年までの間に中国研究人員を2割増やし71万6000人に達するとされており、昨今の中国経済の停滞、脱中国の動きを踏まえても依然として大きな存在であることは変わらないでしょう。各社が中国で投じるR&D費は年間7兆3200億円にも達すると言われ、R&D投資は地元企業の投資と合わせると欧州各国の合計に匹敵し、米国のみが上回る状況にあります。
欧米企業が中国にもつR&D拠点の位置づけは中国国内市場について学ぶ場からイノベーションへの苗床へと変貌していると言われ、外資系企業も、中国の頭脳とイノベーションに配慮した規制体系こそ、自社を世界的成功に導く重要な要素と捉え続けています。新薬から空飛ぶタクシーに至るまでの最新技術を中国ほど素早く試せる場は世界中どこにもありません。
中国へのR&Dが集中するのには以下の理由が挙げられます。
- 若い人材が豊富であること
- 優れた技術を開発する中小企業が数多く存在すること
- 技術者がかなり「お買い得」であること。多くが欧米で学び、働いた経験を有し、才能は欧米技術者に引けを取らず、加えて賃金はかなり安く、米国の3分の1程度(博士号取得者)と言われます。欧州研究員に比べた労働時間も3割長いと言われます。
- 製品化を促進可能な開発環境:化粧品では消費者反応を他市場より素早く試すことができる。製薬でも臨床試験(治験)を欧米よりも安価に実施できる世界一流の委託研究機関の広大なネットワークを活用できる。中国人は治験への参加に他地域よりも前向きであること。
研究開発におけるイノベーションの潮流
研究開発力強化に向けたこれまでの取組み
前述した社会・企業を取り巻く市場環境の変化に伴い、研究開発のアウトプット向上策として、産学官でのコラボレーションに多くの企業が取組んできており、現在も精力的に進められています。協業パートナーとしての代表的存在である産総研(産業技術総合研究所)では、企業と研究所での研究開発成果の社会実装化を促進する為の仕組み(AIST Solution設立)や大型共同研究への取組みを積極化する動きも始まっています。
企業間コラボや産官学間でのコラボレーションの動きは今後も不可欠な手法として継続すべきプロセスであることは間違いありません。しかしながら、ステークホルダーを抱える企業経営者は、自社の成長をより確実なものとすべく、CVCを通じた研究開発投資に踏み切る企業も増えてきました。100億円を超える規模の投資をCVCに行っている企業が多くあります。自社での研究開発を進めながら、社外に少なからぬ費用を投じてその成果を求めていく動きは何を物語っているのでしょう。これまでの自社中心の研究開発手法での取組みだけでは、成長に繋げる見通しに不安があることが一因にあるのではないでしょうか。前述した研究開発環境の変化がもたらした結果と言えるかもしれません。
新事業の源泉を外に求める動きは成長を目指す企業にとっては今後も変わらないでしょう。一方で自社技術をベースとする企業での研究開発活動の重要性も今後も変わらないと思われます。つまり、事業における競争優位性を保持し続ける為に、これまで以上に研究開発力を強化しなければならないと言うことだと思います。
マテリアルズ・インフォマティクス(MI)への期待
研究開発力の基盤は人材にあることは今後も変わらないと思いますが、その生産性向上に向けた有力な方策に、データ駆動型材料研究開発ツール、MIがあると言えるでしょう。今日、多くの企業がMIに関心を示し、研究開発基盤として取込むべく試行錯誤しています。この状況は日本のみならず、欧米・中国でも同様になされていると理解すべきであり、研究開発基盤への取込みを如何にして早期に実現するかは競争優位性確保の為に重要になってきています。しかしながらMIのような新技術は、水が上から下に自然に流れるように、自然に流れて浸透してはくれません。研究者自らの汗水垂らす努力により実現できるものであり、MIを基盤技術として取り込むべく不断の努力が今不可欠です。
研究者の皆さんのその努力をサポートしていくのがMI-6の使命です。MIの導入が、日本企業が世界をリードし続ける為の研究開発力へのイノベーションとなること、その結果として日本企業が世界をリードし続ける存在で有り続けることを心から期待しています。
参考文献
- STARTUP DB 2024年世界時価総額ランキングより
- 文部科学省 科学技術・学術製作研究所「科学技術指標2023」を基に産総研が加工・作成
- 日本経済新聞掲載記事「欧米R&D拠点、中国に残るか」2024年7月23日、「日本の研究力低迷(科学技術指標2024から)」2024年8月20日