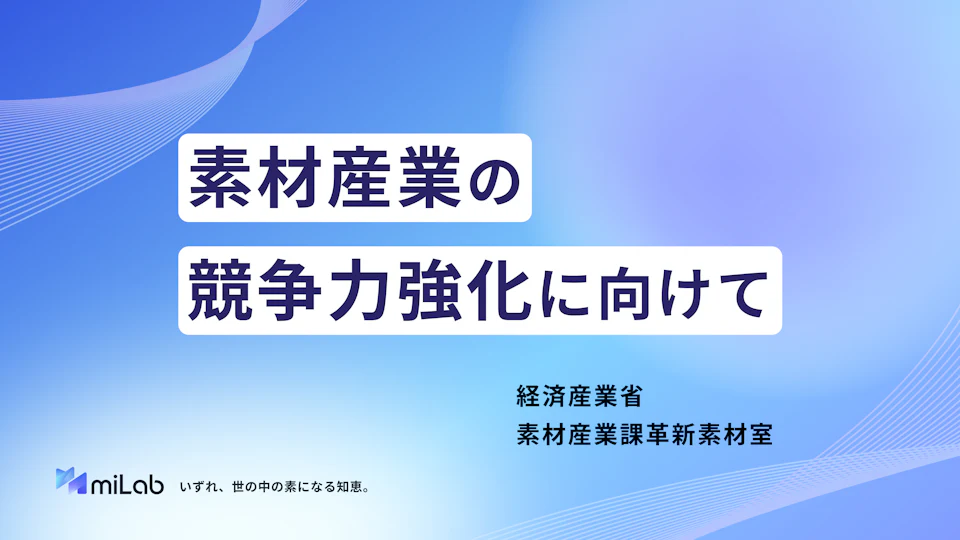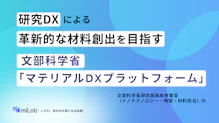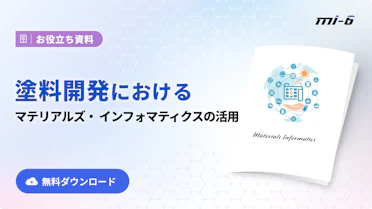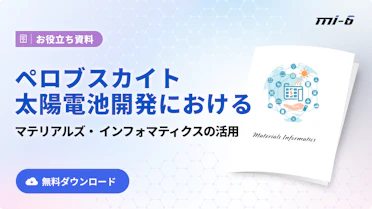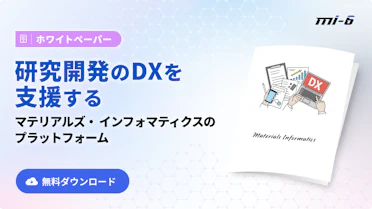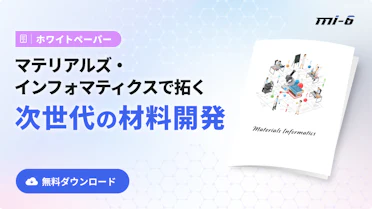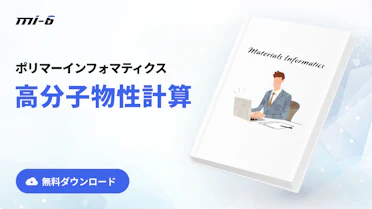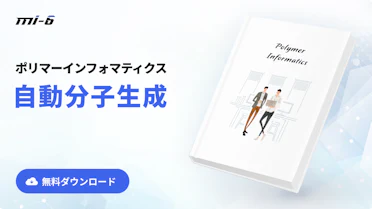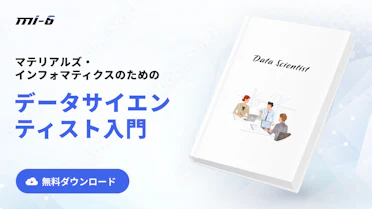はじめに
化学産業を含めた日本の素材産業は、自動車、電機電子、医薬品、消費財など、経済社会に不可欠な製品・サービスになるものを提供し、経済・社会全体を支える基幹産業であり、まさに我が国における競争力の源泉ともいえる産業です。
その中で、日本はいわゆる「機能性化学品」において高い競争力を持ち、最終製品が外国製であっても、その素材は日本製、という製品も少なくありません。日系の素材メーカーは半導体材料や蓄電池材料などの機能性化学品分野をはじめ、世界シェアや収益率が高い製品を有しているところです。
素材産業におけるイノベーションは、カーボンニュートラルの実現という地球的課題の解決に必要となるだけでなく、日本の産業競争力強化や経済社会の安全確保の観点からも重要となります。
本記事では、素材産業の国際競争力強化とカーボンニュートラルの実現に向けた政策動向、その中における「データ駆動型研究開発の取組」を紹介します。
素材産業におけるGX推進
我が国のCO2排出量のうち、製造業は約3分の1を占め、その生産プロセスにおいて大量の電気や熱を消費するエネルギー多消費産業でもあります。その中でも、化学・鉄鋼などの素材産業は、国内の産業部門のCO2排出量の8割を占めます。例えば、石油化学工業では、化学品製造の最上流にあるナフサ熱分解炉で相当量のCO2排出があり、また最終製品のプラスチックについては、サーマルリサイクル等による熱利用の過程でもCO2を排出します。カーボンニュートラルに向けては、産業ごとに、熱源の転換、原料の転換、さらに原料の循環など、きめ細かい対策を講じる必要があります。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、多くの産業が脱炭素化に取り組むなど産業構造が変化する中で、素材産業の動向としては、人口減少などを背景に国内需要が緩やかに減少傾向にある一方、海外需要は引き続き伸長傾向にあり、グローバルでの競争環境は一層苛烈になっております。
政府としても、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の三つの同時実現を目指し、2022年夏以降にグリーントランスフォーメーション(GX)の議論が加速しております。具体的には、2023年2月にはGX基本方針が閣議決定され、同年5月にはGX推進法が成立、7月にはGX推進戦略が閣議決定されております。こうした動きを踏まえつつ、2023年度から試行された「GXリーグ」は、2024年度には700を超える事業者などが参画しております。本取組では、我が国の温室効果ガス排出量の5割超をカバーしており、排出量取引制度の2026年度本格導入に向けて、検討が進められている。また国によるトランジション・ボンドでは世界初となる、「GX経済移行債」の発行や、2023年末には「分野別投資戦略」が取りまとめられ、足下から今後10年程度のGXの方針が提示されました。
こうしたGX政策を進める中、政府は事業環境の予見可能性を高め、日本の成長に不可欠な付加価値の高い産業プロセスの維持・強化につながる国内投資を後押しするため、GX実行会議において産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討し、より長期的視野に立った「GX2040ビジョン」を策定し、2025年2月に閣議決定しております。
素材産業においては、プラスチックなどの化学品製造におけるCO2排出削減を目指し、燃料転換・原料転換に向けた革新的技術開発支援の取組として、グリーンイノベーション基金を活用し、下記4つの研究開発項目のもと、11個のテーマの研究開発を進めています(2021年度から9テーマ実施、2024年度に2テーマ追加)。
- 熱源のカーボンフリー化によるナフサ分解炉の高度化技術の開発
- 廃プラ・廃ゴムからの化学品製造技術の開発
- CO2からの機能性化学品製造技術の開発
- アルコール類からの化学品製造技術の開発
これらの研究開発の成果を社会実装していくため、「分野別投資戦略」において、化学産業のGXの方向性とGX経済移行債を活用した投資促進策について取りまとめており、素材産業のGXを後押しする支援事業として、『CO2排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業』を2024年度より開始しております。
さらに、生産段階でのコストが高いことなどの理由から投資判断が容易でない分野を対象に、企業の新たな国内投資を引き出すため、生産・販売量に応じた税額控除措置を行う「戦略分野国内生産促進税制」が設立しております。具体的な対象分野としては、電気自動車(EV・FCV・軽EV・PHEV)、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料(SAF)、半導体(マイコン・アナログ半導体)を対象とし、特にグリーンケミカルにおいては、化石燃料に由来するものを除いたケミカルリサイクルやバイオケミカルなどを用いて製造した基礎化学品を対象としています。
競争力と経済安全保障
日本の素材産業は、カーボンニュートラルへの対応に加え、諸外国の技術キャッチアップや国際情勢の不安定化によるサプライチェーン不安が高まる中、川下産業と川上産業との連携の強化や、サプライチェーンの強靭化に向けた対応が必要不可欠となっています。
政府としては、2022年に「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保に関する法律(経済安全保障推進法)」を制定し、経済安全保障上重要な物資の安定供給に向け、サプライチェーンを強靭化すべく、設備投資や研究開発などの支援に取り組んでいます。
また、安全保障環境が複雑化する中で、企業単独による技術管理には限界があることから、「技術管理強化のための官民対話スキーム」を構築し、2025年1月から運用を開始しました。我が国が不可欠性や優位性を持つ技術の中から指定した重要技術に関して、官民が対話を行い、直面する現状・課題を共有することで、政策的支援を含む課題解決に向けて取り組むこととしています。
素材産業におけるデータ駆動型研究開発
近年では、DX、AI、ロボティクス、評価・分析技術、計算技術等の関連技術に著しい進展があり、これまでにない素材開発が可能になっております。特に、マテリアルズ・インフォマティクスやプロセス・インフォマティクスといった、AIを活用した新素材開発、そして生産性・収益性向上を目指した研究開発や製造技術確立が加速しています。
経済産業省としましても、例えば、以下のような取組を支援しています(先端計算科学等を活用した新規機能性材料合成・製造プロセス開発事業)。
- 少量多品種の機能性化学品について、フロー式連続精密生産によって高効率に合成するプロセスを確立するとともに、プロセス・インフォマティクスによって短時間で合成経路等を探索する技術を確立する。
- ファインセラミックスについて、製造の各工程における計測技術 (焼結現象の可視化等)と、工程全体を解析できるプロセスシミュレータ等を開発し、6Gデバイス等に求められる「超小型化・高信頼化」に必要な技術を確立する。
また、国内企業においても、材料開発におけるデータ活用やDX関連投資・人材育成の実施、自社の物性データを活かした製品提案サービスといった取り組みも加速しております。
我が国の研究者人口が減少しつつある中で、激化する国際競争に対応するためには、素材産業において、マテリアルズ・インフォマティクスやプロセス・インフォマティクスを活用し、研究開発を高速化、効率化することが不可欠です。
試行錯誤・経験を活かした従来の研究開発手法に計算科学やデータサイエンスを融合することにより、研究開発や製造プロセスを更なる効率化が見込まれます。また、マテリアル開発の国際競争が激化する中で、革新的機能を有するマテリアルをいち早く創出する手法として期待されます。
最後に
GX、DX、経済安全保障といった新しい経済の軸に合わせ、成長につながる投資の形や事業分野の中身も変わっていきます。このように、外部環境が大きく変化する時代において、次の世代に世界で勝負できる成長産業を残し、また創っていけるかは、現役世代の我々に懸かっています。
素材産業は、我が国製造業の競争力の基盤です。我が国製造業全体の競争力の強化を実現すべく、素材産業における競争力の強化に向けた施策の立案・実行に取り組んでまいります。