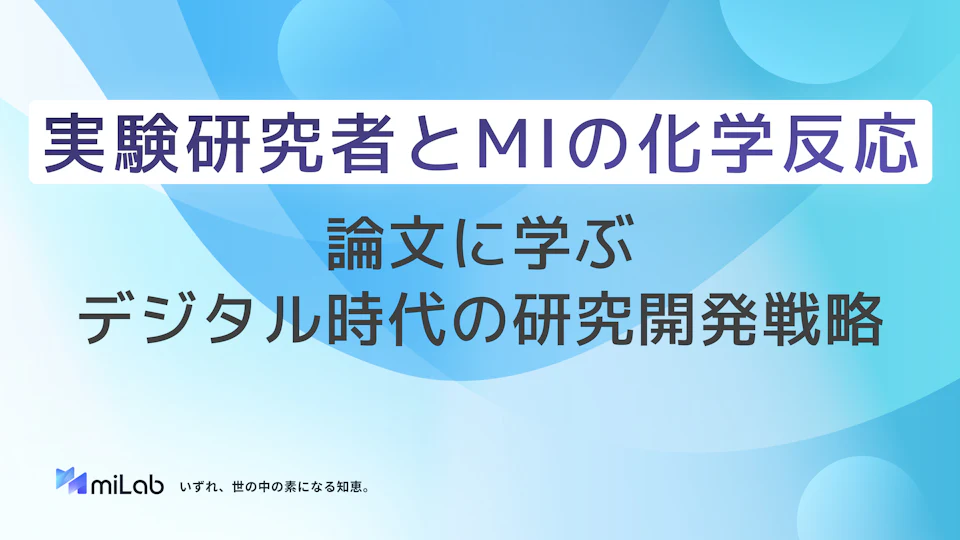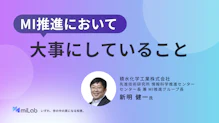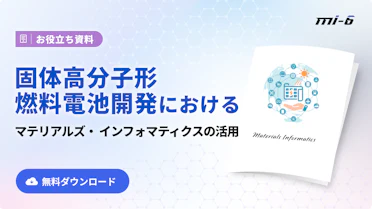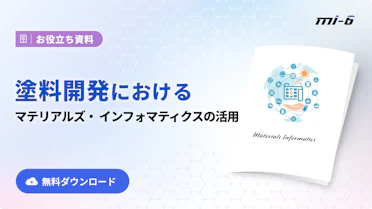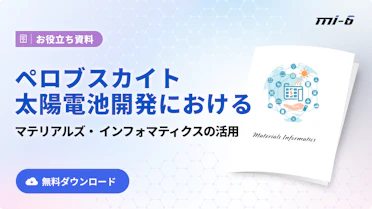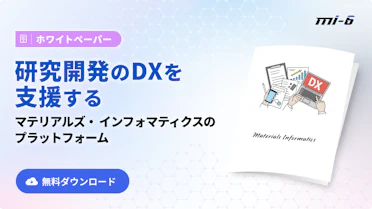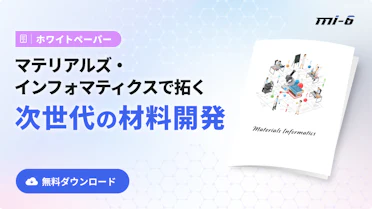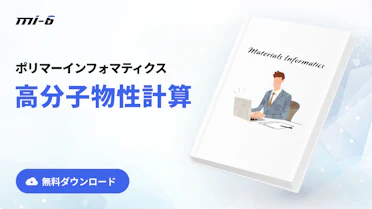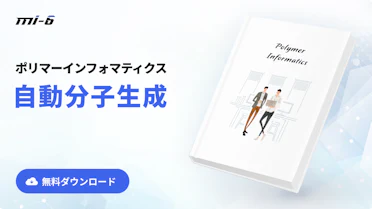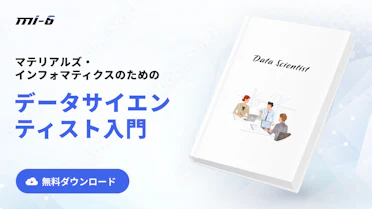なぜ「実験研究者 vs MI」の二項対立は適切な問いではないのか?
材料開発の現場では、長年の経験に裏打ちされた「ベテラン研究者の知見」が、これまで数々の革新的な製品を生み出す原動力となってきました。一方で、近年注目を集めるマテリアルズ・インフォマティクス(MI)は、データサイエンスを用いた材料開発という新たなアプローチとして期待されています。この状況から、「ベテラン研究者とMIは、どちらが優れているのか?」といった議論、いわば「人間 vs AI」の対立構造で語られることが少なくありません。しかし、この二項対立は、これからの研究開発を考える上で本当に適切な問いなのか、疑問を投げかけたいと思います。
ベテラン研究者のドメイン知識は、いわば「暗黙知」の集合体です。複雑な現象の中から本質を見抜き、有望な実験条件にたどり着く上で、そのドメイン知識を含む「暗黙知」は非常に有効です。しかし、その思考プロセスは言語化や形式知化が難しく、属人化しやすいという側面もあります。組織内での技術やノウハウの引き継ぎが難しい、あるいは、なぜその結論に至ったのかを客観的に説明しにくい、といった課題に心当たりのある方もいらっしゃるかもしれません。今回取り上げる論文事例である「半導体のプロセス開発」のような複雑な現場では、今なお熟練した技術者が自身の経験と直感に頼り、試行錯誤を繰り返しながら開発を行っているのが実情です。
なお、ここでいうドメイン知識とは、単なる物理法則や化学反応式の知識だけを指すのではありません。例えば、「この原料メーカーのロットは、前回と微妙に特性が違う傾向がある」「この種のポリマーは、特定の添加剤に対して非常に敏感に反応する」「この評価装置は、こういう条件下ではノイズを拾いやすい」といった、言語化されにくい現場ならではの知見、いわば「勘どころ」の集合体です。これらは、AIが学習するためのデータセットには現れてこない、極めて重要なコンテキスト情報なのです。
一方、AIは膨大なデータから、人間では気づきにくい法則性を見つけ出すことを得意とします。しかし、その性能は学習データの質と量に大きく依存するため、一つのデータ取得に多大なコストと時間がかかる材料開発の分野では、「スモールデータ問題」が常に課題となります。ここに、ベテラン研究者のドメイン知識が活きる道筋が見えてきます。

図1. 人間 (ベテラン研究者)とAI (データサイエンス)の得意・不得意の比較図
出所:著者が作成
この両者の強みを掛け合わせる鍵こそが、研究者のドメイン知識をAIのアプローチに活かすという発想です。例えば、「この材料系では、このパラメータはあまり効かないはずだ」「まずはこの範囲から試すべきだ」といった研究者の直感や経験は、AIが学習する際の有力な方針となり得ます。闇雲に探索を始めるのではなく、有望な領域に絞って探索することで、AIはより少ない実験回数で、求める答えにより早くたどり着くことができます。
つまり、真に問うべきは「人間か、AIか」という二者択一ではなく、「人間の知見をいかにしてAIのアプローチと融合させるか」というハイブリッドな視点なのです。
人間とAIのハイブリッド型開発モデル「HF-CL戦略」とは
「人間とAIは、どのように協働すれば研究開発を加速できるのか?」この問いに、具体的な答えを示したのが、科学論文Natureに掲載された「Human-machine collaboration for improving semiconductor process development」という論文です。この研究では、半導体製造におけるプラズマエッチングという非常に複雑なプロセス開発を題材に、人間とAIのハイブリッド型開発のあり方が検証されました。

図2. 半導体製造における化学プラズマプロセスの開発の流れ
参考文献1より引用。この図はCC BY 4.0ライセンスに基づき利用しています。
研究チームは、この検証のために、実際の実験を模したバーチャル空間での「プロセス開発ゲーム」を構築しました。プレイヤーは、圧力、プラズマパワー、ガスの流量、ウェハ温度など11種類ものパラメータを調整し、最も低いコスト(実験回数)で目標の形状を作り出すことを目指します。これらのパラメータの組み合わせは天文学的な数にのぼり、手当たり次第に試すことは不可能です。このゲームで、①ベテラン研究者、②若手研究者、③AI単独、そして④人間とAIが協働するチーム、のパフォーマンスを比較しました。

図3. 今回のパフォーマンス比較の対象と検証結果
出所:参考文献を参考に著者が作成
このゲームの結果、人間とAIが協働したチームが最もすぐれた結果となりました。 まず、経験豊富なベテランエンジニアは、開発の初期段階、つまり何の手がかりもない状態から有望な条件を探し出す「ラフチューニング(探索的アプローチ)」の局面で優れた能力を発揮しました。彼らは物理や化学の基本原理に基づいた仮説を立て、広大なパラメータ空間を効率的に絞り込んでいったのです。一方、AIアルゴリズムは、ある程度有望な条件が見つかった後、目標値の厳しい制約条件をすべて満たすために微調整を繰り返す「ファインチューニング(活用的アプローチ)」の局面で、人間を上回るパフォーマンスを示しました。この段階では、複数のパラメータが複雑に絡み合うため、人間の直感よりも統計的な最適化を得意とするAIに軍配が上がりました。
この結果から導き出されたのが、「Human First-Computer Last (HF-CL) 戦略」と名付けられたハイブリッド型開発モデルです。これは、その名の通り「最初は人間、最後はコンピュータ」という役割分担を意味します。具体的には、まず経験豊富な研究者が自身のドメイン知識を駆使して、広大なパラメータ空間の中から有望そうな領域を特定し、初期の実験データを提供します。その後、その初期データを引き継いだAIが、ベイズ最適化などの手法を用いて、その領域内で最も効率的な探索を行い、最適なプロセスを見つけ出す、という戦略です。
このHF-CL戦略を用いることで、熟練技術者が単独で開発を行った場合と比較して、目標達成までにかかるコスト(実験回数)を約半分に削減できることが実証されました。AIが単独で開発に挑んだ場合、成功率が5%未満と非常に低かったこととは対照的です。この結果は、人間の直感や経験知がAIの強力なコンテキスト情報となり、探索効率を飛躍的に向上させることを明確に示しています。
成果を最大化する、人間とAIとの役割分担やそのタイミング
HF-CL戦略の有効性が示された一方で、この研究は「人間とAIの協働は、ただ組み合わせればうまくいくという単純なものではない」ということも示しています。その成否を分ける最大の鍵は、「どのタイミングで人間からAIへメインの役割を引き継ぐか」にあります。論文では、人からAIへバトンタッチするタイミングによって、最終的なコストが劇的に変化することが示されています。
論文では、人間からAIへ引き継ぐデータ量(=人間の実験コスト)を変えながら、最終的なトータルコストがどのように変化するかが検証されました。その結果、特定のタイミングで引き継ぐことでトータルコストが低く抑えられるという、特徴的な「V字型」の関係性を示すことが明らかになったのです。

図4. HF-CL戦略における半導体のプロセス開発にかかるコストを評価したV字カーブ(橙色の折れ線) a, b, cはベースをベイズ最適化とする異なるアルゴリズムを用いた検証結果
参考文献より引用。この図はCC BY 4.0ライセンスに基づき利用しています。
このV字カーブが意味するのは、次の通りです。
- 引き継ぎが早すぎる場合(V字の左側):AIに与えられるデータが少なすぎます。これではAIも丸投げ状態からのスタートに近いため、どこから探索を始めてよいか分からず、効率的な学習ができません。結果として、AIが多くの試行錯誤を要するため、トータルコストは高止まりしてしまいます。
- 引き継ぎが遅すぎる場合(V字の右側):人間がファインチューニングの領域まで深入りしすぎている状態です。この段階では、パラメータ間の相互作用が複雑になり、人間の直感だけでは最適解を見つけるのが困難になります。この領域では、人間による実験の「質」が頭打ちになり、コストだけが積み上がっていくのです。人間がコストをかけて試行錯誤を重ねた後にAIに引き継いでも、その時にはすでに人間が行った非効率な実験が「コスト負担」となっており、AIによる削減効果が相殺されてしまいます。
最もトータルコストが低くなるのは、V字の谷底にあたる「最適な点」です。この点が、人間とAIそれぞれが最も得意な領域で力を発揮すべき役割分担を、明確に示しています。これは、人間がドメイン知識を活かして探索空間を十分に絞り込み、かつ、人間が苦手とする精密な探索に入る直前のタイミングと言えるでしょう。このポイントは、言い換えれば「人間の直感の価値が最大化され、一方でその限界が見え始める点」とも表現できます。
- 人間の役割:経験に基づいたドメイン知識と暗黙知に基づき、広大な可能性の中から「筋の良い」初期仮説を立て、AIが探索すべき有望な領域(制約された探索範囲)を定義すること。
- AIの役割:人間によって絞り込まれた領域内で、多変量の複雑な関係性を考慮しながら、人間では見逃しがちな最適なパラメータの組み合わせを、統計的に最も効率の良い手順で探索すること。
成功の鍵は、お互いの得意な領域を見極め、最も効果的なタイミングでバトンを渡すことにあるのです。そのためには、自分たちの開発プロセスにおいて「どの段階から試行錯誤の効率が落ち始めるか」を客観的に見極める視点も重要になるでしょう。
留意点として、今回の結論はあくまで仮想実験上での単純化した事例にすぎません。そのため、現実での様々な研究開発現場での活用を考えると、ここまでは人間、ここまではAIというきれいな線引は難しい点には注意が必要です。今回の例は人間とAIの得意なアプローチとその違い、また両者を融合させたアプローチの重要性について理解するためのユースケースとして活用してください。
AIの”非合理な一手”を取り入れられるか?乗り越えるべき心理的な壁
HF-CL戦略のような人間とAIのハイブリッド型開発は、技術的な側面だけでなく、私たちの働き方や組織文化にも変革が必要になります。論文では、このハイブリッド型開発を阻む可能性のある「心理的な壁」の存在が示唆されています。
論文の中でも、人間とAIの実験の進め方には明確な違いがあったと報告されています。経験豊富な技術者は、過去の知識に基づき、一度に一つのパラメータだけを変更する(単変量解析)など、結果を解釈しやすい実験を好む傾向がありました。 これは、因果関係を理解しながら、着実に目標に近づいていこうとする人間の思考プロセスを反映していると言えます。
それに対し、AI(特にベイズ最適化などの手法)は、複数のパラメータを同時に大きく変更する多変量解析的なアプローチを取ることがあります。 時には、目標からわざと遠ざかるような一見「非合理」とも思える実験を提案することさえあります。 これは、チェスや囲碁のAIが、人間のトップ棋士には思いもつかないような手を指すのに似ています。 AIにとってこのような手は、決して非合理なものではありません。むしろ、現在のモデルが最も不確かだと判断している領域をあえて探索することで、より正確なモデルを構築し、最終的により良い解(大域的最適解)にたどり着くための、極めて合理的な「探索行動」なのです。

図5. 人間の単変数での探索とAIの多変量での探索のイメージ
出所:著者が作成
人間から見れば「失敗」に見える実験結果も、AIにとってはモデルの精度を向上させるための重要な学習データとなります。このAIの思考回路を理解し、「一見、遠回りに見える提案」を許容できるかどうかが、ハイブリッド型開発の成否を分けます。ハイブリッド型開発の実現のためには、研究者個人と組織マネジメントの観点でそれぞれポイントがあります。
研究者個人の観点では、実験を「学び」と捉え、失敗=ネガティブではなく、「モデルの限界や前提の見直しにつながる仮説検証のフィードバック」と捉えるマインドセットが大切です。失敗を許容し、新たな試みに挑戦することを奨励するような、心理的安全性の高い組織文化を醸成することが不可欠です。組織マネジメントの観点では、「意味のある失敗を責めない」「まずはチャレンジを称賛する」といったメッセージを発信し、心理的安全性を担保することで、失敗を許容できる土壌をつくりやすくなります。このように、短期的な成果や目先の効率だけを追い求めるのではなく、失敗も含めた試行錯誤のプロセスから得られる長期的な知見の蓄積を評価する。そのような研究開発組織の変革が、中長期的には必要になります。 これを理解して実際に日常業務で実践するのは簡単ではありませんが、まずは研究者一人ひとりがそのようなスタンスでMIの出力結果を捉えなおしてみる姿勢から始めてみましょう。
明日から始める「人間とAIのハイブリッド型開発」に向けた3つのステップ
では、論文で示されたような人間とAIのハイブリッド型開発を、自分たちの組織で実践するためには、何から始めればよいのでしょうか。壮大な構想を掲げる前に、まずは着実に実行できる3つのステップから始めてみることをお勧めします。
ステップ1:必要最小限のデータのデジタル化とデータ整理
人間とAIによるハイブリッド型開発の大前提は、AIが学習できる形式のデータが存在することです。多くの組織では、過去に行われた貴重な実験の条件、結果、そしてベテラン研究者が残した考察メモなど、価値ある知見が紙のノートや個人のPC内に「暗黙知」として様々な形式で散在しているのではないでしょうか。
最初のステップとして、MIを実践する上で必要な最小限のデータをデジタル化し、構造化したデータセットを構築することから始めましょう。最初から大規模なデータベース構築を目指すと、MIの実践に入る前に頓挫するリスクがあるため、まずはスピードを重視して小さく始めることがポイントです。本格的なデータ整理は、本当に必要な項目が明確になってからでも遅くありません。
データを整理する際は、パラメータ名や単位を揃え、誰が見ても理解できる形にすることが、のちの活用度を大きく左右します。特に、成功データだけではなく、目標を達成できなかった「失敗データ」も、「このルートは有望ではない」とAIに教える貴重な学習データとなるため、同様に価値があることを認識しておきましょう。
ステップ2:スモールスタートでMIに触れる
いきなり大規模なプロジェクトにMIを導入しようとすると、現場の負担や心理的な抵抗が非常に大きくなりがちです。まずは、比較的単純な課題や、過去にデータがある程度蓄積されているテーマを選び、小規模にMIを導入してみる「スモールスタート」を推奨します。コーディングを1から学ぶと時間もかかってしまうので、まずはノーコード/ローコードツールから始めてもいいでしょう。
例えば、「全く新しい機能を持つ分子をゼロから設計する」といった壮大なテーマではなく、「既存の製品の添加剤の配合比率を最適化して、特性を5%向上させる」といった、知見が豊富でリスク(=不確実性)の小さいテーマから始めるのが現実的です。目的は、AIがどのような提案をしてどのような挙動を示すのかを、チームのメンバーが実際に体験し、肌で感じることです。小さな成功体験を積むことで、AIへの過度な期待や漠然とした不安が解消され、より現実的な活用イメージを持つことができます。
ステップ3:MIの結果を議論する場を設ける
AIはあくまで手段であり、最終的な意思決定を行うのは人間です。AIの提案を鵜呑みにするのではなく、「なぜAIはこの条件を提案したのか?」「もし試すなら、どの条件を優先すべきか?」「この提案は我々の知見と一致しているか」「この非合理に見える一手には、どんな意図があるのだろうか」といった点を、チーム内で議論する姿勢が重要です。AIを「答え」ではなく「問いや議論の切り口」をくれる存在として活用するのです。ベテランの経験知とAIのデータ駆動的な視点を突き合わせることで、研究者だけでは思いつかなかったような新しいアイデアが生まれることもあります。
このようなハイブリッド型開発の経験を少しずつ積んでいくことが、組織全体のMI活用能力を高め、やがては文化として定着していくための着実な一歩につながります。
「実験研究者 vs MI」という出口のない対立から脱却し、「実験研究者 & MI」という両者のいいとこどりをするアプローチ、すなわちハイブリッド型開発が、デジタル時代の研究開発競争を勝ち抜くための大きなポイントとなると信じています。
本記事に関連するアーカイブ動画「ベテラン研究者 vs マテリアルズ・インフォマティクス!?~ 研究者としてMIとの正しい向き合い方」も公開しています。併せてご活用ください。
参考文献
- K. J. Kanarik, W. T. Osowiecki, Y. Lu, D. Talukder, N. Roschewsky, S. N. Park, M. Kamon, D. M. Fried, and R. A. Gottscho, "Human-machine collaboration for improving semiconductor process development," Nature, vol. 616, pp. 707-711, 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-05773-7.