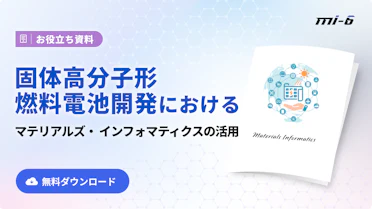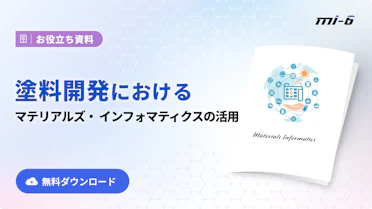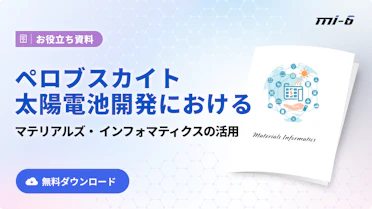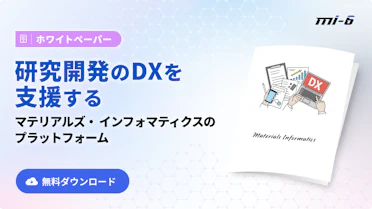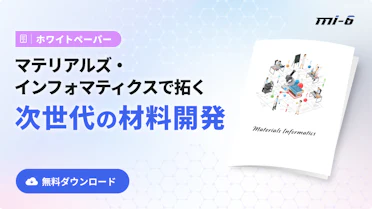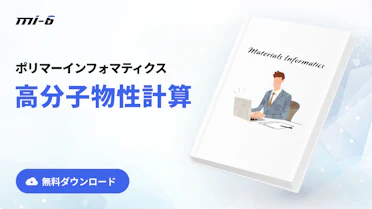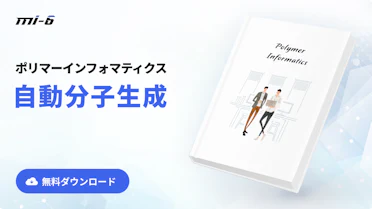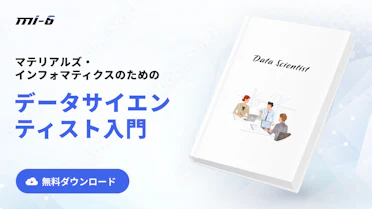材料探索におけるAI推薦システムの必要性
材料設計は、用途や性能要求に合致した新たな材料を見つけ出すための試みです。従来は、機械学習によるデータ解析や最適化手法を用い、評価関数で客観的な基準を設定して材料の性能を数値化し、最適な候補を選定するアプローチで開発を進めることが多いです。しかし、実際の現場では、研究者や職人の感性、すなわち個々の好みや直感が大きな役割を果たすことが多く、評価関数だけでは捉えきれない側面が存在します。このような背景から、あらかじめ定義された評価関数による最適化とは異なり、目的に応じて柔軟に候補を絞り込む手法として推薦システムへの関心が高まっています。推薦システムは、ユーザーの目的や関心に基づいて、多数の候補の中から適した選択肢を提示する仕組みであり、本来は商品やコンテンツの提示に使われてきた技術ですが、その考え方は材料探索にも応用できると考えています。
本稿では、材料設計における推薦システムの基本的な考え方と代表的な手法を紹介し、その可能性と課題について解説します。
材料探索における「推薦」とは?
材料開発における「推薦」とは、研究者が「こんな材料があったらいいな」というアイデアを実現するために、科学的な根拠に基づいて適切な材料を提案するプロセスです。このプロセスでは、まず理想の特性(例:高い耐熱性、低毒性など)を具体的な物性値として定義し、次にその特性を満たす可能性のある分子構造を効率的に探索します。QSPR(定量的構造物性相関モデル)は、この推薦プロセスを支える基本的な手法であり、分子構造と物性の関係を解析することで、未知の材料特性を予測し、最適な候補を提示します。これにより、研究者の抽象的なアイデアを具現化する道筋を効率的に提供します。
推薦システムは、構造から性能を予測するのではなく、目的に合った構造を探すための技術です。性能の数値を正確に求めるのではなく、ユーザーの条件に合いそうな候補を意味的に絞り込むことを目的とします。従来のQSPRが数値予測に基づく設計支援であるのに対して、推薦システムは目的との適合性や選択肢の柔軟性を重視します。ここでは、主要な手法について簡単に紹介します。
コンテンツベースフィルタリング
コンテンツベースフィルタリングは、材料が官能基、分子量、結晶構造などの特徴にもとづいて、目的に合いそうな候補を提案する方法です。注目している材料と構造や性質が近いものを取り上げることで、すでに効果が確認されている材料の周辺から、改良や応用の可能性を広げることができます。この方法は、性能を予測するのではなく、既知の特徴との関係から候補を選ぶ仕組みです。そのため、目的や文脈を深く理解しているわけではなく、あくまで定義された特徴の範囲での提案になります。また、材料の性能は複数の要素が絡み合って決まるため、単純な特徴だけでは判断が難しいこともあります。
協調フィルタリング
協調フィルタリングは、過去にどの材料がどの条件で選ばれたかという選択履歴の関係をもとに、新たな候補を提案する手法です。材料の構造や物性そのものではなく、「どういう目的で、どの材料が実際に使われたか」という選択のパターンに注目します。たとえば、柔軟性と耐熱性を求める場面でポリイミドがよく選ばれていた場合、同様の条件で使われた液晶性高分子などが推薦される可能性があります。構造が大きく異なっていても、「目的に対して成立した選択の実績」に基づいて提案できる点が特徴です。こうした推薦は、候補を眺めながら「この方向性もあるかもしれない」と思考を広げる場面で特に有効です。明確な正解がなく、探索の途中で考えが変わっていくような場面において、履歴に基づく推薦は、次の一手を考えるヒントや着想のきっかけになることがあります。
これらの手法はどちらも、材料の特徴や選択の履歴をもとに、ユーザーの目的に応じた候補を提案するしくみです。推薦の基本的な流れは、「情報を整理し」「好みを反映し」「合いそうな選択肢を提示する」という共通の構造に沿って動いています。

図1. 推薦システムの基本的な流れ
出所:著者にて作成
材料開発における推薦システムの活用例
実験的な材料設計の現場では、性能だけでなく、合成のしやすさや既存の知見との整合性といった、定量化しにくい要素が意思決定に大きく影響します。しかし、これらの専門的な判断は従来の機械学習モデルに組み込みづらく、多くの候補を人手で検討する必要がありました。
この課題に対して提案されたのが、専門家の判断をリアルタイムに推薦プロセスへ取り込む「Expert-in-the-loop型」フレームワークです。この手法により、従来は500時間かかっていたポリマー候補の選定作業が、わずか30分で完了しました。さらに、特許出願レベルの有望な新規モノマーも実際に得られています[2]。
この手法ではまず、既存のモノマー構造を組み合わせて多様な候補を自動生成し、分類モデルによって目的に適合しそうな分子をふるい分けます。次に、専門家が候補を画面上で確認し、有望なものを選択します。選ばれた結果が蓄積され、モデルの推薦精度が段階的に改善されていきます。さらに、専門家が選んだ分子の傾向を学習した生成モデル(GANやLSTM)が、新たな候補を再提案するループも構築されており、専門家の感覚や判断を推薦の流れに組み込むことで、探索の柔軟性と深さが高まります。

図2. 専門家の判断を活用した分子設計の推薦ループ
出所:著者にて作成
推薦システムが開発と運用の課題
推薦システムは、目的に応じた候補を柔軟に提案できる手法として注目されていますが、開発と運用の現場ではいくつかの課題もあります。
- Cold start問題
新しい材料やテーマでは、参考となる履歴がなく、推薦の精度が落ちやすい。 - 情報オーバーロード
候補が多すぎると、かえって選びにくくなり、判断に迷いやすくなる。 - 限られた情報入力
材料の構造や物性といった基本情報に頼らざるを得ず、画像、文献、ユーザーの実験履歴など、多様なデータを統合的に活用するのが難しい。 - 説明性・解釈性
なぜその候補が出てきたのかが見えにくいと、ユーザーが納得して使いにくい。
結論
本記事では、材料探索における推薦システムの基本的な考え方と、代表的な手法や活用のかたちを紹介しました。今後は、LLM(大規模言語モデル)を活用して、言語や知識ベースの情報を取り込むような新しいアプローチについても紹介していく予定です。引き続きご覧いただければ幸いです。
参考文献
- Lops, P., de Gemmis, M., & Semeraro, G. (2010). Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends. In Recommender Systems Handbook (pp. 73-105).https://doi.org/10.1007/978-0-387-85820-3_3
- Ristoski, P., Zubarev, D. Y., Gentile, A. L., Park, N., Sanders, D., Gruhl, D., Kato, L., & Welch, S. (2020). Expert-in-the-loop AI for Polymer Discovery. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM '20) (pp. 2701-2708). Association for Computing Machinery.https://doi.org/10.1145/3340531.3416020
- Sundin, I., Voronov, A., Xiao, H., Papadopoulos, K., Bjerrum, E. J., Heinonen, M., Patronov, A., Kaski, S., & Engkvist, O. (2022). Human-in-the-loop assisted de novo molecular design. Journal of Cheminformatics, 14, Article 86.https://doi.org/10.1186/s13321-022-00667-8