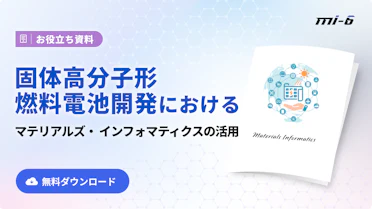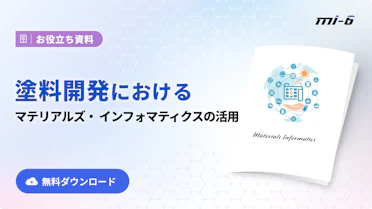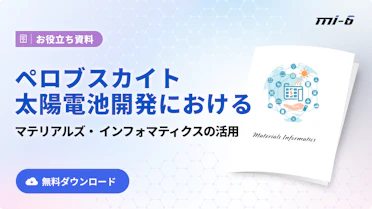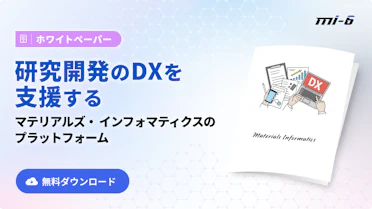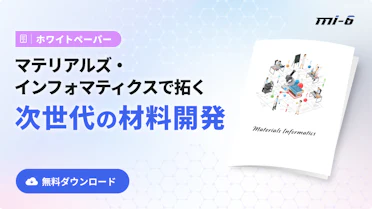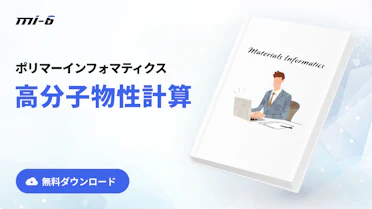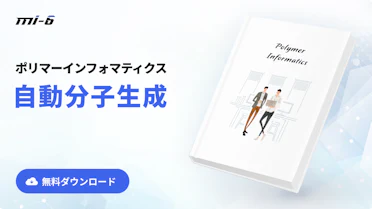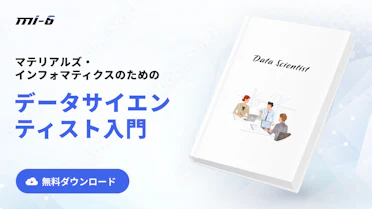近年、研究開発DXの導入・推進はますます加速し、単なる試験的導入を超え、組織レベルでの定着と拡張 にシフトしています。マテリアルズ・インフォマティクス(MI)やデータ活用を起点とした変革の波は、企業・アカデミアを横断しながら広がりを見せており、業界全体の競争力を左右する要素となりつつあります。
MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催し、過去最多となる1,800名以上の方々にお申し込みいただきました。
大阪大学大学院 佐伯教授のご講演では、「DX計測と機械学習による次世代太陽電池の研究」をテーマに、次世代太陽電池の現状・展望や、時間分解マイクロ波伝導度法(TRMC)を用いた実験探索・ラボオートメーションについて、分かりやすく解説いただきました。
本記事では、参加者の方から積極的に頂いた多数のご質問に対して、佐伯教授から開催後にご回答いただいた内容をご紹介いたします。

佐伯 昭紀
Akihiro Saeki
大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻 教授
2007年大阪大学大学院工学研究科応用専攻 博士(工学)取得。2003年大阪大学・産業科学研究所 助手・助教、2010年大阪大学大学院工学研究科・助教、2014年同・准教授を経て2019年より現職。この間、2009年JSTさきがけ「太陽光と光電変換機能」、2015年同「マテリアルズインフォ」、2023年JST-CREST「未踏物質探索」研究代表者。2008 年IUPAC Prize for Young Chemists、2013年文部科学大臣表彰若手科学者賞、2019年 高分子学会日立化成賞などを受賞。次世代太陽電池、高分子、ペロブスカイト、機械学習、ラボオートメーションなどの研究を展開。
自動実験システム・ロボット導入に関して
自律化実験に向けたロボットの導入について、ロボットの導入はどのようにして進めていったのか詳細をお聞きしたいです。従来の実験作業からどの工程にフォーカスしたのか、ロボットの検討、外部業者の検討、測定装置との連動をどのように進めていったのかなど。
ロボット選定のきっかけはMI-6で使っているのを見たことですが、実際に私が行いたい測定系を自動化する際は、治具の設計に加えてマイクロ波回路と測定機器、光学系、駆動系などをソフトで制御する必要があります。各コンポーネントは購入していますが、ソフト・制御はすべて自前です。
製作した自動実験ロボットの製作の期間と費用はどれぐらいかかったのでしょうか?
ここでは具体的な金額は書きませんが、機器と治具の購入実費だけを積算した金額を人に言うと、安い!と言われます。開発期間は実質約1か月です(機器発注・納入の待ち期間を除く)。
ロボットを用いた自動測定システムに関しては、スライドを拝見するに機器導入を進めたのではないかと思いますが、その際ロボットに通底した研究室等との連携はあったのでしょうか。
他のラボとは連携していません。すべて自前です。
弊社もロボットを導入したいと考えておりますが、導入したあとで、困ったことなどはございますでしょうか?
DENSOのCobottaを使用しています。やはり最初は自前ソフトとの接続で苦労しましたが、後は大きな問題はありませんでした。
材料開発・特性予測に関して
セシウム・ビスマス・アンチモン・ヨウ素(Cs-Bi-Sb-I)からなる非鉛太陽電池の発電効率の理論値は、鉛系に比べてどれくらい向上が期待できますか?
バンドギャップが2eV程度なので、理論限界効率は約22%となりますが、実際はそれより低いところが現実的な限界です。ただ、タンデムセルのトップセルや室内光発電などでは有用な光物性を有しています。
TRMCの測定と最終デバイス性能のつながりについて質問です。TRMCでの評価結果について、続く多段のプロセス条件を各材料毎に最適化できれば、デバイスでも概ね同一の序列の性能になるとお考えでしょうか?それとも、ポテンシャルが低いと見込まれていた材料が結果的に最も高性能になるようなことがあり得ますか(安定性以外の要因で)
TRMC測定は材料の本質的な光電気特性をプローブできるので、理想的には素子(デバイス)性能と相関するはずですが、成膜性や不純物、素子構造などが原因で相関しないケースは多々あります。その場合、それらの問題を解決すれば高い素子性能が出るはずです。
Sn-PVKの予測モデル構築やCs-Bi-Sb-Iのハイスループット評価で得られた知見(例: DIの活用、Brightness STDとΔσの指標化)は、他の未探索の材料群(例: 有機薄膜太陽電池のD-Aポリマー)にも応用可能でしょうか?その適用可能性についてご意見をいただけますと幸いです。
他の材料系にも適用可能と考えていますし、有機薄膜太陽電池系にも本評価・解析法を適用して研究開発を行っています。
ロボットを用いた自動測定システムや機械学習の導入により、従来の実験手法では発見できなかったような、材料特性とデバイス性能の間の新たな相関関係や設計指針が見つかった具体例があれば伺いたいです。
特に成膜プロセスは、これまで可視化・数値化できていないものが多いと考えています。これらを見える化することで、新たな隠れパラメータの発見につながると期待しています。
人材連携・組織体制に関して
自動化の装置について、大変感銘を受けました。こういった一連の装置を作り上げるのは、材料に詳しい人だけでなく、設備に詳しい人やソフトウェアに詳しい人間も必要かと思いますが、どのような体制と期間で作られたのでしょうか?
今回ご紹介したロボットを使った自動TRMC・吸収発光・光学顕微鏡測定装置は、私一人で設計・製作しました。私の研究室では、材料合成も評価測定(ソフト・ロボティクス)もできる人材を育成しており、学生も実際の運用時にコード修正やデバッグなどをやってくれてます。
このような先進的な研究を進める上で、データサイエンティスト、化学者、エンジニアなど、異分野の人材間の連携はどのように図られていますか? チーム形成やコミュニケーションの秘訣があればぜひお聞きしたいです。
私の研究室では、外部のデータ科学者や、化学の中でも異分野(物理化学、有機化学、無機化学)との連携を積極的に進めています。ラボの中でも、有機寄り、無機寄り、データ科学寄りのテーマを扱っている学生がいるので、自然と研究室内でも分野間の障壁がないのが当たり前、という雰囲気をつくっています。
研究者はデータサイエンスの知識を身につけて実務を推進すべきでしょうか、それとも専門家と連携すべきでしょうか?
程度はあるものの、両方できることがベストだとは思います。私の研究室は応用化学専攻に所属しており、データ科学や計測は学部ではほとんど触れることはありませんが、それでも研究室に配属された学生は自主的に機械学習解析などをやってくれています。いいテーマと研究の方向性を提示するのが重要だと考えています。
皆様、いかがでしたでしょうか。
佐伯教授の講演本編では、「DX計測と機械学習による次世代太陽電池の研究」をテーマに、次世代太陽電池の現状・展望や、時間分解マイクロ波伝導度法(TRMC)を用いた実験探索・ラボオートメーションについて、分かりやすく解説いただきました。
ご講演の概要記事についても、ぜひご覧ください。