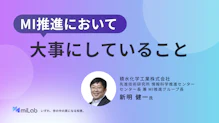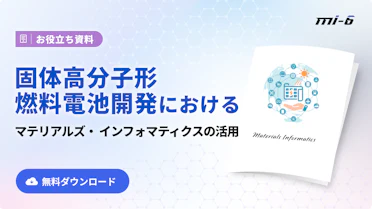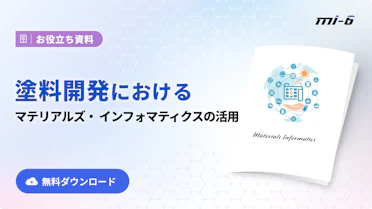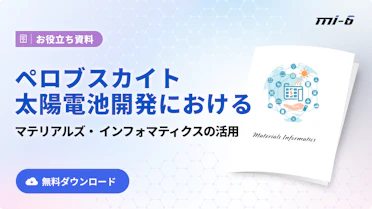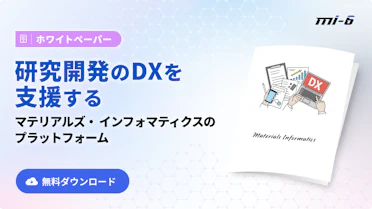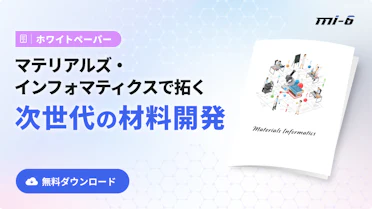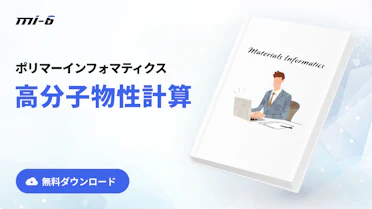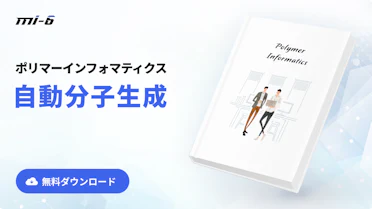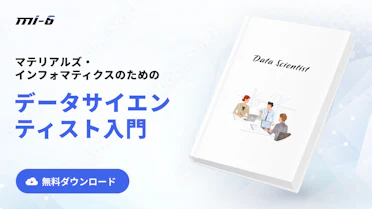カンファレンスの概要
- イベント名称:MI Conf 2025
- 開催日時:2025年 7月 16日(水)13:00〜17:40
- 参加形式:オンライン形式
- 参加者:研究開発、研究企画、DX推進の責任者、データサイエンティスト、学生 等
今年で3年目の開催となるMI Conf 2025では、「研究開発DXの更なる加速へ。最前線の実践知、ここに集結」をテーマに、企業におけるMIの取り組みやアカデミアにおける最新技術の研究など、素材産業に携わる方々にとって必見の内容をお届けしました。
過去最多となる1,800名以上の方々にお申し込みいただき、質疑応答も含めて活発な議論の中で、MIトップランナーの皆様から、貴重な知見を共有いただきました。
オープニングトーク1:素材産業の国際競争力強化に向けた戦略
経済産業省の山田氏は、日本の素材産業が直面する国際競争力強化に向けた戦略について講演いただきました。日本の素材産業が製造業全体の約2割を占めるという重要な位置づけであることに触れつつ、高機能材分野における日本の高いシェアと国際競争環境について説明。あわせて、データ駆動型材料開発に関する国内外の取り組みや課題について、多角的な視点から解説いただきました。
- 登壇者のご紹介
経済産業省 製造産業局 素材産業課 革新素材室 室長 / 山田 純市 氏
オープニングトーク2:マテリアル革新力強化戦略に基づく文部科学省の取組
文部科学省の伊藤氏は、マテリアル革新力強化戦略に基づく取り組みについて講演。
日本の国際競争力を維持・強化するためには、データ駆動型研究開発の効率化・高速化・高度化が急務です。その解決策として同省が進めている「マテリアルDXプラットフォーム」について紹介。データ収集・蓄積からAI活用、ロボティクスとの融合まで、研究DXの基盤整備と推進に向けた具体的な施策を説明いただきました。
- 登壇者のご紹介
文部科学省 研究振興局参事官(ナノテクノロジー・物質・材料担当)付 参事官補佐 / 伊藤 大介 氏
基調講演 1:とある素材開発グループにおけるMIやロボット実験活用の現実と課題
JFEスチール株式会社の須藤氏には、機能性材料(粉体)の表面改質による高性能化をテーマにご講演いただきました。
Materials Projectなどのデータを活用した材料選定や、自律的物質創製ロボットを用いた薄膜の熱処理条件最適化など、実際の取り組み事例を交えてMI導入の現実と課題が解説されました。さらに、これらの技術導入によって開発期間を大幅に短縮できた効果についても具体的に紹介され、MIと実験自動化の組み合わせが生産現場にもたらす可能性が示されました。
- 登壇者のご紹介
JFEスチール株式会社 スチール研究所サステナブルマテリアル研究部 グループリーダー / 須藤 幹人 氏
基調講演 2:次世代MIのための高精度第一原理計算技術
北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)の本郷氏には、次世代MIのための高精度第一原理計算技術についてご講演いただきました。データ駆動型材料開発が加速する中、MIにおける理論的手法や、基盤となる第一原理計算の最新の進展について解説されています。
大規模なスーパーコンピュータを活用した計算材料科学の重要性が示され、未知物質の探索や合理的な実験設計を可能にする手法をご紹介いただきました。
- 登壇者のご紹介
北陸先端科学技術大学院大学 情報社会基盤研究センター 准教授 / 本郷 研太 氏
基調講演 3:潤滑油の商品開発におけるMI活用
コスモ石油ルブリカンツ株式会社の貝戸氏は、潤滑油の商品開発におけるMI活用について講演されました。数百種類の基材・添加剤から最適配合を見出すために、過去データの構造化やAIによる予測・推奨を活用し、研究開発を効率化した事例を紹介。
ガスエンジン油開発では、少ない実験回数で目標性能の処方設計を達成した例や、放熱材開発でデータ蓄積に伴いモデル精度が向上したことなど、MIが実際の成果につながる様子を具体的にご説明いただきました。
- 登壇者のご紹介
コスモ石油ルブリカンツ株式会社 技術部 次世代事業開発グループ / 貝戸 信博 氏
基調講演 4:DX計測と機械学習による次世代太陽電池の研究
大阪大学大学院の佐伯氏は、DX計測と機械学習を活用した次世代太陽電池研究についてご講演。ペロブスカイト太陽電池や有機薄膜太陽電池の現状とともに、TRMC法(時間分解マイクロ波伝導度法)を活用したハイスループット実験やラボオートメーションの活用事例についても詳しく解説されています。
また、非鉛材料群の探索やSn-PVK素子の性能予測モデル開発などの事例を通じて、データ駆動型アプローチが材料探索と研究効率化に果たす役割が強調されました。
- 登壇者のご紹介
大阪大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 教授 / 佐伯 昭紀 氏
基調講演 5:レゾナックにおけるMIの組織活用・推進
株式会社レゾナックの奥野氏は、MIの組織活用・推進をテーマに講演されました。ポリマー特性解析や混合溶媒最適化、レジスト開発といった研究開発課題に対して、量子コンピューティング技術なども組み合わせたAI活用の具体事例が紹介されています。
さらに、データパイプライン構築やウェブアプリによる現場展開など、MIを組織的に浸透させるための仕組みについてもお話しいただきました。
- 登壇者のご紹介
株式会社レゾナック 計算情報科学研究センター フェロー 計算情報科学研究センター長 / 奥野 好成 氏
基調講演 6:MIによる素材・材料開発の進化と成果創出へのアプローチ
積水化学工業株式会社の新明氏は、MIによる素材・材料開発の進化と成果創出について講演。全社的なMI展開を通じ、フィルム製品の開発期間短縮や接着剤開発における新規材料発見の成功事例が紹介されました。
また、MI活用による事業貢献を実現するための課題設定や、人材育成の仕組み化についても具体的に説明されています。MIと実験自動化を組み合わせた今後の展望にも言及いただきました。
- 登壇者のご紹介
積水化学工業株式会社 先進技術研究所 情報科学推進センター センター長 兼 MI推進グループ長 / 新明 健一 氏
ご参加者の声(事後アンケートより)
カンファレンス当日参加者のアンケートでは 平均満足度4.4(5段階)と非常に高い評価をいただいております。
- 幅広い業界、幅広いテーマの講演がそろっており、多くの学びを得ることができ大変満足しています
- 成功事例だけではなく苦労していることやどう物事を捉えながらMIを推進するかなど様々な意見を聞けて良かったです
- 昨年よりもMIの活用レベルが上がっている気がいたしました。また、カンファレンス全体の内容が大変濃かったと感じました
最後に
皆様、いかがでしたでしょうか。各講演ごとの記事も今後、順次公開してまいります。データ駆動型研究開発は試行錯誤の連続ですが、本イベントが皆様の「成功確度の高い試行」を後押しし、「成功するまで試行し続ける」原動力となることを願っています。