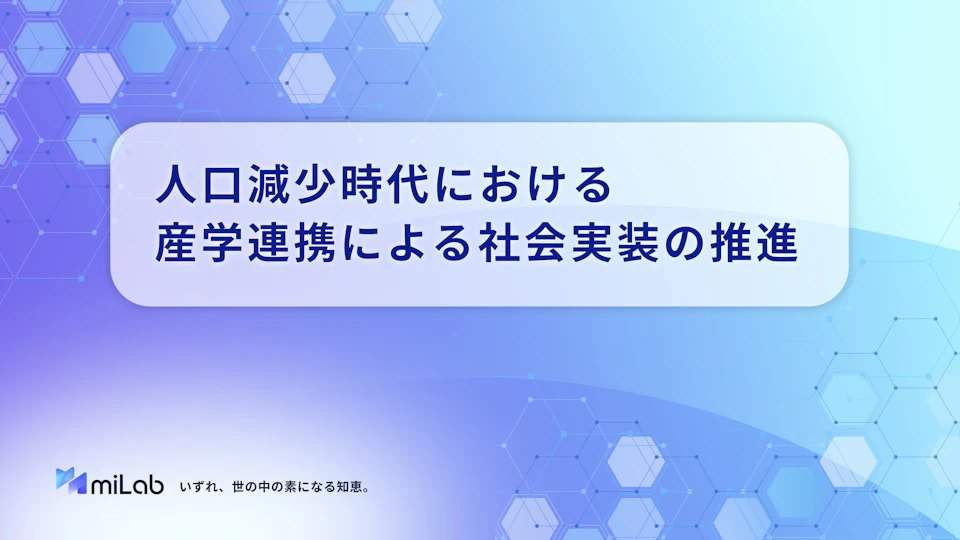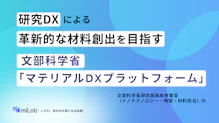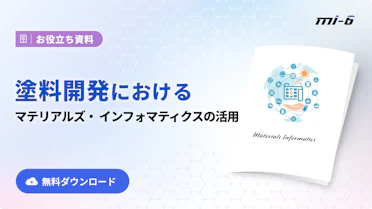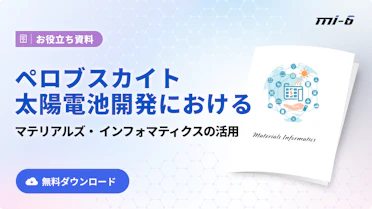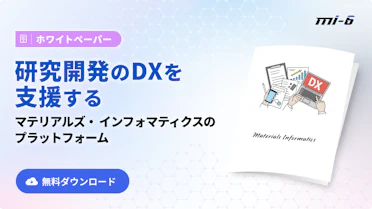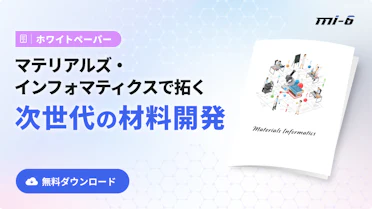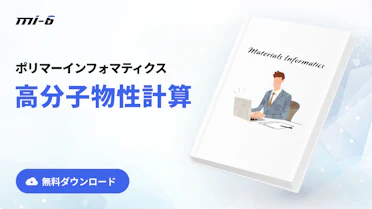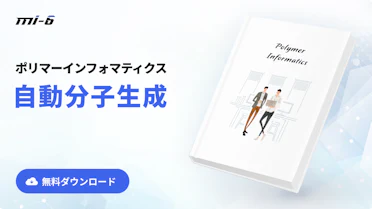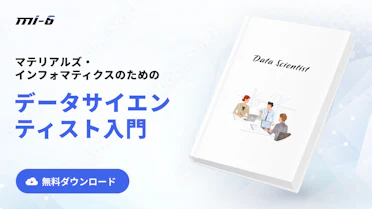環境問題、エネルギー・食料危機、少子高齢化への対応、そして人々のウェルビーイングを実現するためには、研究開発に関わるオープンイノベーションと産学連携の推進が不可欠である。本稿では、著者自身の経験をもとに、産学連携の現状を紹介し、社会実装とイノベーションを目指した新しいモデルを提案したい。
自己紹介
寄稿依頼をいただいた際、心の奥底に潜んでいた“材料研究者だった日々”の記憶が鮮明に蘇ってきた。私は大学院生から国立研究所の研究員として、25年以上にわたりセラミックスを研究する人だった。世界最高水準の高熱伝導率を持つ窒化物(AlN、Si3N4)セラミックスの開発に成功し、その事業化にも貢献した。しかし、この一連の開発には多大な資金と長い期間が必要となり、産業用の工業材料として広く活用に至るまで20年以上の月日を要した。
現在では、MI(マテリアル インフォマティクス)などデータ駆動型アプローチの導入により、研究情報の取得や研究計画の作成、効率的な実験が「迅速」かつ「当たり前」として行われつつある。また、研究データの蓄積や情報基盤の構築、専門家同士の知識共有が進み、真のニーズに応える“価値創造”の研究スタイルの構築が進んでいる。元研究者として、MIを活用した材料開発がさらに進展することを大いに期待している。
私は研究現場を離れた後、企業出向をへて、国立研究所本部の産学連携とイノベーションを推進する部署へ異動し、研究成果の社会実装やイノベーション推進に関わる業務を担当した。これらの経験を通じて、研究成果の社会への還元において、産学連携と社会実装の仕組みづくりや、そのオペレーションが重要であることを実感した。本稿では、これまでの経験にもとづき、産学連携の現状を述べ、社会実装やイノベーションに向けたモデルを紹介したい。
イノベーションと産学連携
日本のイノベーション力は、2007年に世界第4位、2015年には第19位、2023年と2024年には第13位に落ち着いている。現在、アジア諸国ではシンガポール(第4位)、韓国(第6位)、中国(第11位)に次ぐ順位である。WIPOの報告によれば、日本のイノベーション推進における課題は、制度や機関の在り方、人材資本と研究、そして創造的アウトプットの弱さにある1)。また、2024年の世界競争ランキングでは、日本は第38位と前年から順位を下げており、OECD加盟国中でも最低レベルである2)。
日本のイノベーション推進においては、2014年当時に次の3つの構造的課題が指摘されていた。
(1)制度・構造の壁
- ライフサイエンス研究における臨床研究の不備と治験審査体制の限界
- 実証研究への社会的受容性の不足
(2)人材と人材流動性の欠如の壁
- 研究成果と事業化の間の乖離
- 終身雇用制度の弊害
- 優秀な外国人研究者の内部資源化や有効活用できない組織体制
- 職域や組織内外を超えた融合型研究体制の構築の難しさ
(3)研究情報価値の形成の壁
- 研究成果と企業ニーズのマッチングや価値共有の困難さ
- 研究成果へのアクセスにおける内外格差
- 要素研究から展開型研究への協力体制の弱さ
これらの課題は、優れた研究成果を創出しても、事業化や社会実装、イノベーションに繋がらない原因となっている。このことが、日本経済の30年間にわたる長期停滞の一因と考えられている。
壁を打破するための取り組みと成果
上記に示した壁を克服するため、オールジャパンで産学連携の環境整備が進められている。具体的な取り組みとして、次の施策が行われている。
- 予算の増額: 政府による産学連携や研究活動の支援に重点を置いた財政的強化。
- オープンイノベーションの推進: 企業と大学、研究機関の垣根を越えた連携協力に関するガイドラインの策定、企業の研究開発減税の拡充
- 専門職員の充実: University Research Administrator(URA)、企業出身のコーディネータ、知財専門職などの採用と強化。
- 人材交流の活性化: クロスアポイントメント制度や、不利益を被らない企業人材の研究機関への出向支援の充実
- 組織間連携の強化: 冠ラボ・企業ラボ設置、オールジャパン型や民活型コンソーシアムの推進。
- スタートアップ支援: ベンチャー企業の育成を積極的に推進。
これらの施策により、日本の産学連携は2014年当時と比較して大きな進展を遂げ、その成果は企業共同研究の契約数や提供資金額の増加といった数値として現れている。しかしながら、企業から大学や公的研究機関への研究資金は、2019年度で年間約1600億円であり、企業全体の研究資金(約20兆円)のわずか0.8%に過ぎない。この割合は、他国に比べて依然として低い水準である3-5)。今後の連携強化を通じて、企業との共同研究成果が実用化され、その利益の一部が循環して、大学や公的研究機関へ共同研究資金して再流入するエコサイクルができることを期待したい。具体的な産学連携の施策と活動例として、産業技術総合研究所の評価委員会資料を参考文献に示した6)。
制度・構造の壁については、我が国は他の先進国と比較して明らかに遅れている状況が続いている。一方で、いくつかの企業や組織は、実証研究を通じて社会実装を推進する取り組みを進めている。例えば、以下の事例が注目されている。
- 日立製作所は、医療分野での実証研究を進めるため、北海道大学および周辺市町村との組織連携を行っている。この連携により、医療技術の社会実装が着実に進むことが期待される7)。
- トヨタ自動車は、実証実験の街「Woven City」の稼働を2025年秋に予定している。このプロジェクトは、未来のスマートシティの構築を目指し、実証研究を通じて技術革新を促進する重要な試みである8)。
これらの活動は、制度・構造の壁を徐々に克服し、社会実装の推進に向けた先行的なモデルとして位置付けられる。
社会実装力の強化
日本は、世界をリードする研究成果を数多く発信している。しかし、この数10年間企業が先端技術を取り込み、新製品や新サービスを生み出す力は急激に低下している。この原因の一つは、社会変化に迅速に対応できる組織体制や仕組みの不備にあると考えられる。
日本発の研究シーズは、産学連携を通じて企業などとの共同研究に繋がり、その後企業内での事業化ステージへと移行する。しかし、多くの場合、関連する知的財産が取得されているが、時間の経過とともに事業化の道が閉ざされていく傾向にある。本来であれば、共同研究成果と企業が保有する技術がアセット化され、それを基盤に高付加価値で強い競争力を持つ製品やサービスが市場に出ることが理想である。
一方で、研究情報は特許出願や論文発表を通じて、時間差なく世界に広く公開される。その後、豊富な研究予算、資本力、マンパワーを持つ他国企業や研究所が参入し、事業化を主導する事例が多々見られる。この結果、日本発の独創的な研究成果が他国によって事業化されるケースが増えている。
このような現状を踏まえると、研究から事業化、社会実装までのプロセスを円滑に進め、社会実装に向けて迅速かつ柔軟に対応できる組織の構築が急務である。具体的には、人材バンク的なプラットフォーム(共通基盤)の整備が必要とされる。現在、国プロの研究成果をスムーズに社会に出すための組織として、「技術研究組合制度」が創設されている。この制度は、将来的には株式会社化を視野に入れた新しい産学連携モデルとして注目される9)。
社会実装を推進する産学連携
人口減少時代に入った日本では社会全体で人手不足であり、今後の産学連携を通じて社会実装を進める人材の確保は更に深刻である。このような状況下で、社会実装に向けて、“幅広い”業務を“高速”に、“柔軟“に対応できる組織を考えると、図1に示す外部人材の“積極的”活用による伴走支援型産学連携となる。

図1. 少子化時代に対応する伴走支援型 社会実装推進 産学連携モデル
構成する人材については、次のような人材をイメージしている。
- プロデューサー:研究成果を事業化する司令塔として、全体の統括とプロジェクト推進のエンジン役
- 社会実装を推進するための研究開発人材:コアとなる研究開発を進めるとともに、様々な要素技術をアセット化し、優位性および、コスト競争力を持った事業性の高い新製品及び新サービスに仕上げる人材。
- 事業化に直接・間接的に関わる人材:事業化を高速に進めるために、事業化に関わる実務経験と深い専門性を持つ人材
- 高度なスキルを有する多様な人材:事業におけるネットワーキングの拡充やバランスの良い成長をするために、事業化に関わる実務経験のあるプロ専門家
伴走支援型産学連携では、コアとなるのは「プロデューサー」と「研究開発人材チーム」である。ここの組織体制がしっかりしていないと、伴走支援型産学連携は機能しない。
海外における事例として挙げられるのは、ドイツのフラウンホーファー研究機構である。研究成開発と事業化を同時並行で進めるプログラムを実施し、プロデューサーに権限を集中し、数々の成功を収めている。この制度が長年にわたって上手く回っているのは、若い人材がプロデューサーに就任し、事業化時の様々な経験とノウハウ、技術力、目利き力などを蓄えてキャリアを形成し、その後企業に異動し、トップマネジメント人材となり、ドイツ企業の価値創造に貢献しているためである。ドイツにおける理工系人材のキャリアモデルにもなっている。
伴走支援型産学連携では、「プロデューサー」の存在は大きく、主な役割をまとめると次のとおりである。前記した全体の統括とプロジェクト推進のエンジン役に加え、
- 優れた人材のスカウトとマネージメント
- 多様な人材をまとめ、研究と事業開発を一体的に進める調整役
プロデューサーが一人で負担を抱え込まないために、チーム制を導入し、次世代のプロデューサー候補やサポート人材を加えることが望ましい。
伴走支援型産学連携を成功に導く鍵は、プロデューサーの採用にある。筆者のこれまでの経験に基づくと、成功を収めた、そして機動的に活動する研究開発プロジェクトには、必ず優れたプロジェクトリーダーの存在が見受けられる。その多くは、人格的に秀でており、プロジェクトに対する強い責任感と将来への明確なビジョンを兼ね備え、チームメンバーから高い尊敬と信頼を得ている。
海外の例を参考にすると、ドイツにおいては、プロデューサーの選定が、理系・文系の枠を超え、深い教養と豊かな人間性を持つ人材にも焦点を当てている。歴史や文学を専門とする人材がプロジェクトのトップを務め、優れた成果を挙げる例も少なくないと聞いている。高い専門性を有する個性的な集団を効果的にまとめるには、卓越した調整能力が求められると同時に、その基盤として人格的な魅力、教養、そしてメンバーからの尊敬が不可欠である。
伴走支援やネットワーク型で、事業展開を進めているのが米国のシリコンバレーを中心とした例である。 事業化やイノベーションを先導する企業や個人が複層的なネットワークを形成し、これがスタートアップやイノベーションの成長を支える原動力となっている。
これらの成功例から得られる知見を踏まえると、研究開発から事業化までの一貫性を担うプロデュース型と、外部人材の“積極的”活用による伴走支援型を合わせ持つ社会実装推進が理想とする産学連携モデル(図1)となる。プロジェクトに参画する専門人材は、現在の働き方を反映すると、兼業、副業、業務委託など多様な形態を受け入れる。社会性の高いプロジェクトについては、プロボノ(無償の社会貢献活動)としてスキルや経験を活かしての参加も受け入れるべきである。
社会実装を推進するためには、「幅広い」業務を「迅速」かつ「柔軟」に対応できる組織体制の構築が不可欠である。その鍵となるのが、参集する人材がプロジェクトやその後の社会実装におけるビジョンや価値を共有できるかどうかである。この共有が実現することで、プロジェクトの一体感と成功率が大きく向上する。また、こうした体制には“志のある企業や個人”との連携が欠かせない。このような連携を通じて、互いの強みを活かしたシナジー効果が生まれ、プロジェクトがより効果的に進行すると考えている。
人材流動性と社会実装への期待
自己実現やwell-beingなど、個人を取り巻く社会変化が進むなか、優秀な人材の流動性が増加している。このような人材は、研究開発を基盤とした社会実装を目指すスタートアップやプロジェクトに積極的に携わり、その数が増え続けている。これらの人材は、培った多様な職場経験を活かし、組織の活性化や事業化に向けた取り組みに対して大きな刺激を与えている10,11)。人材の流動性と様々な経験は、我が国における研究開発から事業化、そして社会実装へと繋がる流れを構築するうえで極めて重要である。今後、これらの優秀な人材は社会実装を成功させるための鍵を握る存在として、要の役割を担うことが期待される。
おわりに
日本が抱える現在の課題を考えると、社会実装やイノベーションを強力に推進する組織を全国各地に配置することは急務である。本稿では、産学連携の現状と潜在的な課題を踏まえ、人口減少時代における社会実装を目的とした新しい産学連携モデルを提案した。このモデルが効果的に機能するための問題点や課題については、今後さらに深く検討を進めていく予定である。本記事が、研究成果の社会実装を目指す皆さまにとって少しでも御参考となれば幸いである。
参考文献
1) WIPO, Global Innovation Index 2024
2) IMD, 世界競争力ランキング 2024
3) 例えば、経産省 大学ファクトブック2024
4) OECD Data, Research and Development Statics https://www.oecd.org/en/data/datasets/research-and-development-statistics.html
5) 経済産業省 産業技術環境局、経済産業省における産学官連携に係る支援施策についてhttps://www.jarec.or.jp/30th_jarec_symposium/pdf/workshop_8_11.pdf
6) 産業技術総合研究所 令和元年度及び第4期中長期目標期間 業務実績・自己評価結果説明資料https://www.meti.go.jp/shingikai/kempatsushin/sangyo_gijutsu/pdf/010_04_00.pdf
7) 日立北大ラボwebsite https://hitachi-lab.mcip.hokudai.ac.jp/
8) TOYOTA WOVEN CITY website https://www.woven-city.global/jpn/about/
9) 技術研究組合(CIP)の現況について https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/kenkyuu/cipgenkyou.pdf
10) 令和元年度 「イノベーション人材の流動化に係る要因調査」、内閣府、 令和2年3月 https://www8.cao.go.jp/cstp/package/jinzairyudo/houkokusho.pdf
11) 小野寺、岸、知的資産創造、pp.42-59, 2022年12月