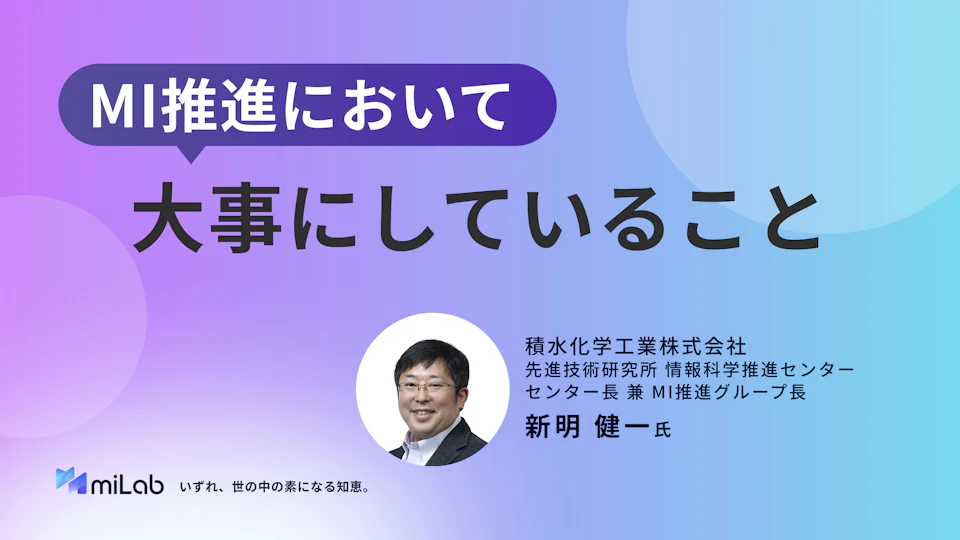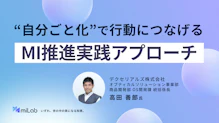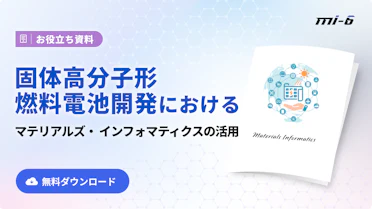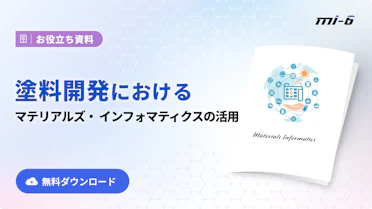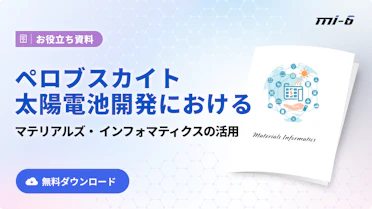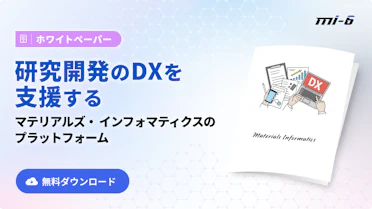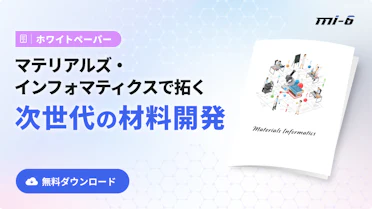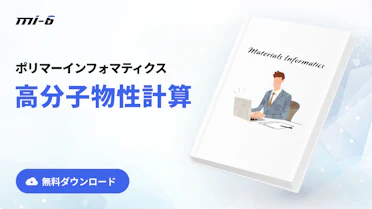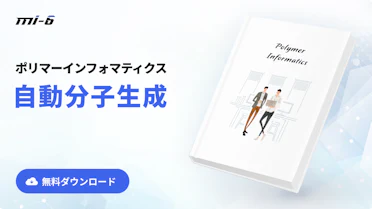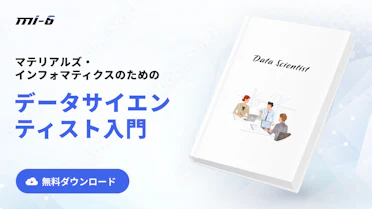はじめに
私はもともと、材料開発に携わるエンジニアです。
学生時代は、光触媒を用いた可視光水分解に関する研究を進めてきました。
社会人になってからは、燃料電池やリチウムイオン二次電池の材料やプロセス開発、CO2をアクリル酸に変換する触媒の開発など、さまざまな材料と向き合いながら10年以上過ごしてきました。
そんな私が、いろいろなきっかけや選択の結果、今、現在はマテリアルズ・インフォマティクス(MI)を中心とする「開発DX」を推進する立場になっています。
ここ数年は、外部セミナーや講演などで、自社が進める素材・材料へのMI活用やそのための組織運営等の題目でお話させていただくこと機会もいただいており、少しずつですが、その取り組みをアピールすることができているのではないかと認識しています。
今回、miLabというオンラインメディアに寄稿するにあたり、せっかくなので、セミナーや講演では、時間の関係で話していなかった「材料開発のエンジニアであった私が、MIを始めたきっかけ、MIを進める上での苦労、そして現在に至った経緯」を、堅苦しくない形で書いてみようと思いました。
というのも、ふと立ち止まって、その経緯をふり返ってみると、そこには一つの流れがあり、多くの材料開発に携わるエンジニアがMIを始めよう、うまく活用していこうとすると、立ち止まった点、苦労した点、そして工夫し乗り越えた点などを含め、おそらく同じような経験をすることもあるのではないかと思ったからです。
最初は、開発部署で材料開発のエンジニアとしてMIを手探りで始めるところから。
やがて、MIを推進する専門部署で社内のさまざまな開発テーマにMIを展開する役割を担い、
そして現在は、情報科学推進センターという会社における開発DXの中核を担う組織を率いて、日々、業務に邁進しています。

図1. 情報科学推進センターの組織体系
現在では、MI※だけで100を超える開発、製造テーマと連携し、そのうち数30を超えるテーマで開発の効率化、提案材料の採用獲得などの成果を創出してきました。
そのいくつかは、すでに世に出た製品への適用を実現しています。
※当社では、MI推進グループ、計算科学グループ、画像解析グループ、そして評価分析グループと技術領域ごとに組織が分かれており、グループ間で連携しながらも、開発課題に適した技術を適用する運用を進めています。
この道のりは、順風満帆ではありませんでした。
さまざまな人、組織の助けを借りながら、連携を進め、多くの失敗を経験しながら、試行錯誤の連続で今に至っています。
だからこそ、これから「自分の部署でMIを始めたい」と考えている方や、すでにDX推進の立場で、どう社内に広げていこうか悩んでいる方にとって、きっと何かしらのヒントになるのではないかと思っています。
これは、一つの事例にすぎませんが
この事例が、今まさにMIや開発DXに向き合っている皆さんの活動の参考に、少しでもなれたなら——それほど嬉しいことはありません。
材料開発のエンジニアとして、ずっと持っていた違和感
私はこれまでに10年以上、材料開発の現場に身を置いてきました。
燃料電池、リチウムイオン電池、そして触媒材料。新しい材料を追い求め、試作と評価を繰り返す日々。自ら手掛けた材料が期待以上の性能を出し、それがユーザーへの提案に繋がることは、何事にも代えがたい喜びです。
また時には国内外を問わず外部の大学、研究機関と連携をしながら開発を一歩ずつ進めることに大きなやりがいも感じていました。
けれど、ある時から、自分自身、そして開発チームの研究開発の進め方に違和感を覚えることが出てきました。
その違和感は、決して大きな問題として現れるものではなく、
むしろ、開発チームの報告の場などで、何か気持ち悪いなと思うくらいで何事も無く開発は進められていきます。
たとえば、過去に自分が取り組んだ検討を、数年後に別のメンバーが“また”始めていた時。
「あれ?これ、前に似たような条件でやっていたはずなんだけどな……」
そう思って記録を探してみるものの、必要なデータは見つからず、結局は一からやり直し。まるで、同じ山を別の登山道から何度も登るような、非効率さ。
そして、チームの誰かが苦労して得た実験結果も、そのままチーム全体に共有されることは少ない。
特に、失敗したデータや、思うような性能が出なかった“うまくいかなかった”結果ほど、記録に残らずに埋もれていく。だから、また同じことを数か月後、数年後に繰り返してしまう。
そこには学びがあるはずなのに、次に活かされない。だから、また誰かが同じ失敗を繰り返してしまう——そんな場面も少なくないように思います。
もちろん、従来のやり方がすべて悪いわけではありません。
経験と勘、手を動かすことによって得られる“現場の知恵、知見”には、他に代えがたい価値があり、MIを進める立場になっても、その重要性は変わることは全くありません。
一方で、経験と勘のみに頼り切った開発、そして、過去のデータ、知見を活用できない開発では、未来は無いのではないか。
そんな確信にも似た想いを強く抱くようになったのは、2017年、私がCO₂の資源化に取り組む触媒材料※の開発に本格的に挑戦し始めた頃のことでした。
※開発していた材料は、金属酸化物で、自身が酸化還元することで、CO2の反応を促進するので、厳密には触媒ではないのですが、表現の簡易化のために触媒と呼ぶこととしています。
触媒材料の開発は、実に複雑です。
配合の組み合わせは膨大で、少し構成比を変えるだけで性能ががらりと変わる。
さらに厄介なのは、触媒を調整する方法、焼成温度、時間などのプロセス条件や、成型条件、さらには、それらの組み合わせによっても性能が大きく左右されるため、同じ配合、条件でも再現性が取りづらい。
やっと試作が終わっても、評価には非常に時間がかかります。1つの触媒を評価するのに、結果が出るまで半日から丸一日ももかかるため、データはなかなか蓄積されない。
まるで、霧の中を手探りで進むような、そんな開発の連続でした。
私はもともと開発の効率化に興味を持ち、2008年ごろから実験計画法、品質工学を燃料電池材料やリチウムイオン電池の開発に適用してきました。
10年近くにわたり30以上の事例に活用し、いくつもの開発の効率化を実現してきました。
実験計画法、品質工学も広く見ればデータドリブンで開発を進める手法です。
これをより高度に使いこなすことで、我々が今抱えている課題を解決できないか。
その想いがMI(マテリアルズ・インフォマティクス)の活用をはじめる、最初の一歩となりました。
2015年ごろから日本でもMIを推進するMI2Iや超超プロジェクトなどの大型のプロジェクトがいくつも立ち上がり、多くの製造業がそこに参画したことは記憶に新しいと思います。
残念ながら当社はここに参画しておらず、業界の取り組みから大きく後れを取っていました。当時、MIについて調査を始めたばかりのころ、その現実に強い危機感を覚えたことを今でもよく覚えています。
MI導入プロジェクトの立ち上げ
2018年、研究所内で小さな動きが始まろうとしていました。
その年、研究所内で「MI導入プロジェクト」が立ち上がるという話が持ち上がりました。
プロジェクトの内容は明確ではなく、むしろ“未知”そのもの。
でも私は、迷わず手を挙げました。
「触媒材料の開発にMIを使ってみたい」——と。
先に述べた通り、当時、私は長年、品質工学に取り組んできていました。
実験計画法、品質工学、統計的思考……。それらの知識をベースにしながら、より高度に活かせるのではと考えました。
そうして始まったのが、私も含め4人ほどの小さなMI導入プロジェクト。
チームの誰もが、MIについてはド素人。
手探りどころか、真っ暗な森の中に地図なしで飛び込んだような状態でした。
プロジェクトが始まった当初、社内の反応は、正直言うと冷ややかというか無関心な状態でした。
それは当然も当然で、当時は、MIがどういったものかを知っている人は多くなかったですし、AIで何か新しいものを提案するなんて、そんな都合のいい話はないと思われていたのかもしれません。
今振り返ると、最初の段階における周りの無関心が逆にプロジェクトの推進にとてもよかったと感じています。
あまり注目されていない分、変な周りの圧力に左右されることなく、開発を前に進めるために必要なことについて、を利害関係を持つ関係者=プロジェクトにコミットした人で議論し、プロジェクトを進められました。
特に、他部署の統計解析を専門とする若手のエンジニアが、本プロジェクトに興味を持ち協力してくれたことが、今思うと大きかったと思っています。
のちほど述べますが、触媒材料データを用いた実解析においては、次元圧縮による可視化や機械学習などの解析技術を持っていなかった当時のプロジェクトメンバーにとっては、スモールスタートを完遂するに重要な役割を果たしてくれました。
外部のセミナーや講演の場でも特に強く主張しているのですが、プロジェクト開始時の体制構築は、当たり前ですがプロジェクト成否に大きく影響します。

図2. プロジェクト推進における体制構築の重要性
共通の課題認識を持ち、そこに何かしらの役割りをコミットして、目的、目標を持って活動できないプロジェクトは途中で崩壊します。
それは内部だけではなく、外部の要因も深くかかわります。プロジェクトの目的を理解しない外部からの働きかけはその典型例かもしれません。
これは、決して外部を入れずにクローズにやるべきという意味ではありません。
むしろ、自組織のトップ(当時の私の場合で言えば、触媒開発グループ長や、研究所長)に、プロジェクトの目的、目標を理解してもらうまで説明し続け、理解者、協力者になってもらう必要があります。
これは、外部との共同研究や設備投資が必要なプロジェクトで特に大事なことだと思います。
プロジェクトマネージャーの役割りは、まさにここに集約されると認識しています。
必要な体制をつくり、役割りをコミットして、プロジェクトの目的、方向性を定めること、そして、それを上位層に説明して理解者、協力者となってもらうこと、この2つは、当たり前のことのようで、なかなかできないことですが、これができるかできないかでプロジェクトの成否が大きく変わってきます。
私自身も多くのプロジェクトマネジメントで痛いほど経験してきました。
話を戻します。
MI導入のプロジェクトメンバーは、もちろんのこと、研究所内にいても当時MIについて知識も技術も持っていませんでした。
だからこそ、自分たちで取りにいくしかないとやる気のあるメンバーがあつまりました。
整理すると、自身を含む触媒開発メンバー3人と、他部署の統計解析を専門とする若手メンバー1名、計4名のプロジェクトです。
この時の進め方でよかったなと思う1つのことは、MI活用に知見を持つ専門家との連携体制を最初に作れたことです。
いわゆるコンサルティングですが、その専門家は、メーカーでの豊富な材料開発の経験と先行したMI活用を推進していた方で、早期に世の中の推進状況や、相談や連携すべき専門家を特定することができました。
後発で進めることの大きなメリットは先人が試行錯誤してきた過程を飛ばして、活用できることです。
これを利用しない手はありません。
それをもとに、複数の大学との共同研究を立ち上げ、MIの第一人者たちと接点を持ち、学術的な知見を必死に吸収しました。
開発部署でのMI活用の模索
MI導入プロジェクトが立ち上がった——とはいえ、最初から何かがうまく回り始めたわけではありません。
むしろ、「何から手をつけていいのかすらわからない」。それが最初の現実でした。
だからこそ、私はまず、自分たちなりの“地に足のついたスタート”を切ろうと考えました。
繰り返しになりますが、
最初に行ったのは、スモールチームの立ち上げです。
当時私が担当していた触媒材料の開発メンバーを中心に、社内で統計科学に明るい有識者にも参加してもらい、異なる視点を持ち込む体制を整えました。
さらに、MIに精通した外部のコンサルタントをアドバイザーとして迎え、実務は私たちが担いながら、戦略的な伴走支援を受ける形にしました。
加えて、マテリアルズインフォマティクスや計算科学を専門とする大学の先生方との共同研究やコンサルティング契約も進め、社外からの知見を積極的に取り入れました。
材料科学と情報科学という、これまで交わることのなかった2つの世界をつなぎ、MIを現場で“使える技術”にしていくことを目指しました。
狙ったのは、まず自分達が取り組んでいる触媒開発という一つのテーマで明確な成果を出すこと。
小さくてもいいので、確実な成功を掴み、それを突破口にする―――そのために入れられるリソースはすべて入れる、まずは自分たち自身がMIを活用することで開発に貢献することができると確信を持つことが第一歩だと考えました。
今思うと、4つ以上の大学との共同研究や学術コンサルティングを、こんな初期のプロジェクトに投資していただいたので、当時の上司には頭が上がりません。
とはいえ、当時の我々も、上記の連携を進めるために、ありとあらゆる観点から、何度も説明を繰り返し、何とか進められる算段を必死にさぐっていたことを覚えているので、そういった強い想いが伝わったことも大きかったのかと思います(外部連携等の承認を判断する立場になると、改めて、プロジェクトメンバーの強い想いや本気度は大事だなと感じています)。
MIに精通した外部のアドバイザーがいたとはいえ、自分たちにとってははじめての取り組みです。
仮説をもとにした試行錯誤の連続で、少しずつ前進しながらも多くの失敗もありました。
せっかくなので、振り返ってみようと思います。
良かった点
- 自分たちがドメイン知識を持つ触媒材料の開発にテーマを絞って進めたこと
- 実解析ができる人をプロジェクトメンバーに据えたこと(だけれども、逆に利害関係の無い、興味があるだけの人などをメンバーにいれなかったこと)
悪かった点(今であれば違うやり方をしたと思うこと)
- 自分たちの専門領域ではない触媒材料のシミュレーション技術の活用によるメカニズムの解明を、最初のテーマに設定したこと
プロジェクトメンバーは触媒設計の実実験側の専門家ではありますが、シミュレーションに関しては、ほとんど知見がありませんでした。
だからこそ、こちらに多くの検討工数を割きました。たらればの話にはなってしまうのですが、今、同じ状況だとすると、強みである実実験のデータを活用してのデータの可視化、機械学習モデルの構築による材料探索を進めることに注力します。
結果的には、後述する、本プロジェクトの後半にて取り組んだ実実験データをベースとした検討によって成果が得られる形となりました
そして約一年後、私たちは確かな成果を手にしました。
MIを活用して、過去の実験データ、自分たちのドメイン知識、さらに外部の無機材料データベースを組み合わせて分析。
その結果、これまで誰も注目してこなかった新しい材料の組み合わせを予測することができたのです。
実際にその配合で試作・評価を行ったところ、触媒性能の向上につながる成果を得ることができました。
この取り組みの技術的な詳細は、明治大学の金子先生との共同研究の成果として、ACS Omega(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c00461)にも報告されていますので、技術的な内容に興味のある方はぜひ見ていただければと思います。
情報科学推進センター 仲間が集まり、仕組みが生まれた
MIという新しい技術の可能性に手応えを感じ始めてはいましたが、それをどうやって、自分たちだけではなく周りに広げていくか。
MI導入プロジェクトとしては、次のフェーズに入りましたが、ここからが本当に難しいフェーズとも言えます。
一部の開発テーマで使えるツール——そんな認識が、社内の大半を占めていたと思います。
そんな認識を持った技術者と良好な関係を築きながら、連携する開発テーマについて深く理解していない自分たちが、MIを活用して新しいものを提案する。
ハードルが高いのは想像に難くありません。
当時を思い返すと、私はこのときに自身のキャリアの中心をMIに変えたいと決めた時期だったと思います。
10年以上、材料開発に従事していた自分にとっては、当時を思い返せば、大きな決断だったと感じます。
MIは、単なる“開発手法の一つ”ではなく、ものづくりの在り方そのものを変える力がある。
それを本気で活かすには、個人の挑戦やチームの努力だけでは限界がある。
「組織としての仕組み」へと昇華させなければいけない。 とも考えていました。
その思いが少しずつ形になり始めたのは、2019年ごろのことでした。
MIの取り組みについては、実は社内の別の研究所で1年ほど先行して始まっていました。高機能プラスチックスカンパニーの開発研究所にある「テクノロジーインキュベーショングループ(以下TIG)」が中心となり、MI技術の習得や展開が進められていました。
コーポレートで我々が主導するMI導入プロジェクトも外部連携を進めつつも、TIGのメンバーに積極的に相談に乗ってもらいMI活用に関する多くのサポートをいただいていました。
この繋がりがきっかけとなったと私は考えていますが、この繋がりが点となり、その点をつなぐように、2020年10月、それらが一つに統合され、「情報科学推進センター」が誕生しました。
この組織が特別だったのは、単に“技術導入の窓口”ではなく、全社横断で情報科学を推進するための中核機能として設計されたことです。
材料、プロセス、製品開発、製造、生産技術、知財、品質保証——
あらゆる領域に対して、「情報科学の力」で革新をもたらすことをミッションとして掲げました。
そしてもう一つの大きな特徴は、“人”の集め方にありました。
情報科学推進センターは、社内の公募制度を活用し、「データサイエンティストとして成長したい」と自ら手を挙げた社員を広く募りました。
実際に集まってきたのは、いわゆるITやプログラミングの専門家ではなく、材料開発や現場の第一線で経験を積んできた人たち。
当初は8割以上、現在でも6割近くが、ものづくりの現場を知る人材で構成されているのが、この組織の特徴であり強みです。
MIを推進するデータサイエンティストが、材料開発の経験、ドメイン知識を持つべきという考えは今も変わっていませんし、これからも変わることは無いと思っています。
「情報科学」は技術であると同時に、現場でどう使われるかが問われる領域です。
現場のものづくりを知る人たちが、データと向き合い、手を動かしながらMIスキルを身につけ、独自のデータサイエンティスト(当社ではデータ活用人材と呼称しています)に育っていく。
育ったデータサイエンティストが、開発や製造部署に入り込み、自身の開発経験、ドメイン知識、情報科学技術を駆使して提案する。
それが、積水化学らしいMIのかたちになったと考えています。
ただ、そうした組織が立ち上がったとはいえ、当時の業界全体から見ると、積水化学の取り組みは“後発”でした。
すでに先陣を切ってMIを導入していた企業も多く、我々の立場は「追いつく側」。でも、だからこそ、徹底的に他社の事例を調査し、学ぶことに力を注ぎました。
さまざまな企業と情報交換会を行い、取り組みの背景や課題、工夫を聞き出しながら、「自分たちが進むべき道」を、組織として描くことに時間を惜しみませんでした。
ただ他社の取り組みをそのまま真似をするのではなく、学びを自組織や積水化学の状態に置き換えるとどうなるかを言葉に落とし込み、課題に対する解決の筋道を自分たちの組織構造や文化に適応させていきました。
今思えば、この“ビジョン構築※”に真剣に取り組んだことこそが、今日の成功につながっていると、強く感じています。
※ビジョン構築の部分について、MIを推進するにあたって特に重要な部分だと思っているので、補足しておきたいと思います。
これについてはいろいろな書籍がでているので、詳細の説明はそこに譲るとして、自分なりの考えをまとめます。1つの考え方として受け止めていただければ幸いです。
一言で言うと、ビジョン構築とは、ありたい姿と進むべき方向性を決めることです。
片方が欠けてもいけません。
私は、ビジョン構築に関して、いつも持っているイメージがあります。それは自分が円の中心にいて、円周上にある一点を定めるイメージ(正確には±10度くらいの幅を持つ)です。
円周上の一点があるべき姿、円の中心からその一点を結ぶ線が進むべき方向性です。
多くのプロジェクトに携わってきて、成功する(前に進んでいる)プロジェクトとそうでないプロジェクトを見てみると、この部分が大きな要因を占めていると認識しています。
あまりうまくいかない組織やプロジェクトに、特に多いのが、手を広げすぎていることです。
中長期的視点だからこそかもしれませんが、あれもこれも世の中でトレンドになっている技術や取り組みを詰め込んでしまったビジョンです。
むしろ、取りえる選択肢のなかから、ありたい姿を実現するために、社内環境、社外環境を鑑みて、やるべきことを絞り込むことが特に重要だと思います。
場合によっては、人がもっといれば、これがやりたかったけども、あきらめる決断も必要かもしれません。
また、もちろん、ありたい姿に、メンバー自身がやるべき価値のあるものだと思えるような将来の夢や展望を盛り込むことも重要だと思います。私は、むしろこの部分が苦手(アセスメント研修をやるとこの部分が弱みと出る)なので、こういったことが得意なメンバーとの日々の議論が欠かせません。
MI推進において大事にしていること
MI(マテリアルズ・インフォマティクス)という言葉が、少しずつ社会に浸透しつつある今。
私たちの取り組みもまた、“導入”のフェーズから、“定着と拡大”のフェーズへと進みつつあります。
その中で、改めて、MI推進において何を一番大事にしているのかを、振り返ってみると、その考えは全く変わっていないことに気づきました。
開発者にとっての価値創出にこだわる
当たり前のことかもしれません。
でも私は、この当たり前のことが、MIを習熟すればするほど、できているようでできていない状況になりやすいと考えていますし、そうなってしまい、うまく開発に価値を届けられない事例をたくさん見てきました。
よくあるのが、
精度の高い予測モデルができた。
材料候補の提案スピードが10倍になった。
それはもちろん素晴らしいことです。
けれど、それだけでは不十分ですし、MIに習熟すればするほど陥りやすい罠とも言えます。
問うべきは、「それは、開発者にとって“本当に価値あること”か?」
材料候補の提案スピードが10倍になったとしても、もし、候補材料を実際に作るプロセスがボトルネックになっていたならば、意味がありません。
そこを見失ってはいけないと、いつも自分に、そして組織のメンバーに言い聞かせています。
(おそらくメンバーからは言われなくても分かっていると思われているかもしれませんが、ここについては、それくらいがちょうどいいと考えています)
開発者にとっての価値創造にこだわる、1つの取り組みとして、私たちの組織では、MI活用の相談があったとき、すぐに解析やモデリングに入るのではなく、まず最初にやることがあります。
それは、「そのテーマで、MIを使うことによって、どんな価値が生まれるか?」を徹底的に分析することです。
これも当たり前といえば、当たり前なのですが、
- 開発課題は本質的に何なのか?
- その課題を解決することで、どんなインパクトがあるのか?
- 時間短縮?コスト削減?性能向上? それはどれくらいの価値か?
こうしたことを、開発担当者と同じ目線で、一緒に考えるのが、私たちの基本スタンスです。個々のメンバーで差が出ないように、上記のことを定型的にヒアリングするためのシートを運用しています。

図3. プロジェクト推進前に実施するヒアリングの項目
さらに、連携するテーマについて、定期的に実際にどれだけの価値が生まれたのかを定量的に評価します。
テーマ終了時だけでなく、半期毎に、基本、全テーマについて評価します。
生まれた価値が恣意的にならないように、その評価については、連携する開発テーマの担当者にも確認してもらいます。
非常に手間のかかる、大変な時間ですが、MI推進の個々のメンバーにとっても、自分自身のやってきたことが、開発への価値につながったのか、つながりそうなのか、またそのインパクトはどれくらいか、まだつながっていなければ、何が足りないのか、を振り返り、そして、必要に応じて、進め方を軌道修正できる重要な役割を担っています。
テーマの始まりと終わりの両方で評価軸を設け、センターとして創出した成果を「見える化」していく。
これによって、「やったことがどれくらい価値に繋がったか」が明確になります。
これは、個々のメンバーだけでなく組織としても重要な役割を担っています。
組織全体として、創出した価値を可視化することによって、上位層、経営層へのアピールにつながります。短期的、中期的な視点が必要な大きな取り組みについて、当然、やりやすくなりますし、より安心して投資してもらえることにもつながると考えています
改めてになりますが、
私は、開発者にとっての価値にこだわり、1つ1つ、確実にそれを実現していくことが、MI活用を成功に導く唯一の道だと考えています。
それが開発部署からの信頼となり、ひいては会社全体からの信頼となり、MIそして情報科学が会社の“文化”として広がっていく道だと、私は思っています。
現場の目線に立ち続けること
MIを扱う側も、開発課題を抱えるエンジニアと同じ目線に立たなければならない。
私自身、いつもこう考えています。
「自分がそのテーマの開発担当者だったらどうするか?」
「この解析結果が、製品化の成否を左右するかもしれない。そう思ってデータと向き合えているか?」
そういう“覚悟”と“責任感”をもって、解析や支援に取り組んでいます。
そしてこの姿勢は、私自身だけでなく、情報科学推進センターのメンバーにも常に伝え続けています。
単に「MI技術を使う」のではなく、「自分が開発に関わっている」という意識を持つこと。
自分事にすることで、データは、単なる文字と数値の羅列ではなく、開発者が日々、試行錯誤した思考プロセスや、実際の開発現場が見えてくるようになります。
そして、より深く開発のことを理解することによって、より高度な視点と考察力で解析を進めることができるようになります。
本気で取り組む姿勢は、開発者に必ず伝わり、その継続が信頼につながり、価値を生む原動力になると考えています。
属人的にしない。「技術を、人に閉じ込めない仕組み」をつくる
MIは高度な専門技術である一方で、属人的になりやすい危うさもあります。
一部のエキスパートしか使えない“ブラックボックス”にしてしまっては、組織の力にはなりません。
だから私たちは、早い段階から「仕組み化」に徹底的にこだわってきました。具体的には、特に力を入れて取り組んでいるのが、人材育成の仕組み化です。
もちろん、道のりは簡単ではありませんでした。社内教育カリキュラムを体系化し、初学者でも学びながらMIを使える仕掛けをつくってきましたが、失敗を重ねながら、試行錯誤しながら進めてきました。それでも今、ようやく少しずつではありますが、道筋が見え始めています。

図4. 人材育成の全体像
2020年から、「あるべき人材像」の定義を行い、「育成したMI人材の見える化」を進め、そして、MI人材を育成するための仕組みとして、初学者向けの情報科学セミナーや、より実践的なトレーニングプログラム等を通じて、段階的にスキルを身につけられる場を準備してきました。
MI人材を育成する際に、ボトルネックになったのが解析環境の準備と、RやPythonといったプログラミング知識の習得でした。
それ自身は、今やインターネット上に情報は山ほどありますし、ChatGPTのような生成AIツールを活用すれば、プログラミングの知識が無くとも、やりたいことのコードを簡単に生成してくれます。
それでも、慣れない解析環境で、プログラミングの知識を習熟しながら、さらに、正しく統計、機械学習を使う(例えば、主成分分析の解釈、クロスバリデーションやハイパーパラメータの設定等)ための理解を進めることは、慣れない開発エンジニアにとっては容易ではありません。
これだけが理由では無いと思いますが、種々の教育プログラムに参加した人材が、なかなか継続的にMIの活用を進められない状況が散見されるなどしていました。
幸いにも世の中には優れたデータ解析ツールが存在しており、我々は、目的やエンジニアのレベルに応じて使い分けることを基本の考えとしています。
上記の課題を解決するための1つの取り組みとして進めていることを紹介します。
材料開発のエンジニアが、普段の開発業務で簡便にデータの可視化や解析を、直感的に進められるツールの開発を、MI推進グループのメンバーが中心となって進め、2024年に材料開発に特化した独自のMIアプリ「RASIN」をリリースするに至りました(https://www.sekisui.co.jp/news/2024/1425473_41090.html)。
「RASIN」は、これまで、MI推進グループが、100を超える開発テーマとの連携で蓄積してきた解析技術をすべての開発エンジニアが活用できる形で提供しています。
プログラミング技術が不要なノーコードアプリで、材料開発のエンジニアが直感的に使えるようになっており、さらには、開発エンジニアが正しく活用するための工夫(マニュアル、パラメータ設定、GUI)がされています。まだリリースして1年といったところですが、すでに、開発エンジニアが自立的に「RASIN」を活用して、新製品向け配合の提案を実施する事例などが複数出てきており、MI人材の育成が加速フェーズに入ったと考えています。
常に学びの姿勢
積水化学のMI導入は、業界全体の中では“後発”でした。
少なくとも3年以上は遅かったのではないでしょうか。
でも、今、振り返ってみると、逆に良かったとも感じています。
なぜならば、先行企業のさまざまな取り組みの事例を、彼らの成功や失敗の経験も含めて、数多く知ることができたからです。
得られた膨大な情報をもとに、自分たちで仮説を立て、「自分たちの組織、会社は、どうあるべきか」を考えることができたからです。
何を言いたいかというと、まだ、MI活用が進められていない、うまくいっていないという部署、会社もまだまだ多いのではないかと推察していますが、先行する事例を学び、利用することで、一気に取り組みを加速することができるということです。
我々もうまく進められている部分、進められてない部分があります。うまく進められていない部分は当然のこと、うまく進められていると考えている部分においても、常に学ぶ姿勢をもって、取り組みをより加速できないかを意識しています。
早く始めることは、もちろん大事です。
でもそれ以上に、「なぜやるのか」「何を目指すのか」を明確に持つことの方が、はるかに価値があると私は考えています。
さいごに
気がつけば、触媒材料の開発者から、いろんな繋がりやきっかけで、始めたMIですが、今や専門性を問われれば、MIと言いたくなるほど、どっぷりとこの世界に入り込み、10年近くが経とうとしています。
今、積水化学では、MIを活用するための仕組みが、少しずつですが、確かに根を張りはじめています。
多くの協力部署との連携のもと、情報科学推進センターを軸に、全社の中でMIをはじめとする情報科学技術を開発、製造に活かしていこうとする文化が、少しずつ醸成されつつあります。
現場の開発者と共に価値を生み出し、実績を積み上げ、着実にMIの信頼が広がっています。
けれど、まだまだ「完成」ではなく、
ようやく“あたりまえに使える未来”へのスタートラインに立てたに過ぎないと考えています。
これからも、技術は進化し、特に、近年の生成AIの出現と進化によって、開発のあり方は一層大きく変わり続けていくでしょう。
だからこそ、私たちには「これは本当に、開発者の価値になっているか?」という問いと価値観を持ち続けながらも、立ち止まらない姿勢が求められます。
私たちがMIで目指しているのは、ただの効率化でも、機械任せの開発でもありません。
人がもっと自由に、もっと深く、もっと面白く材料を創っていくための未来です。
その未来を、一緒につくっていけたら嬉しいです。