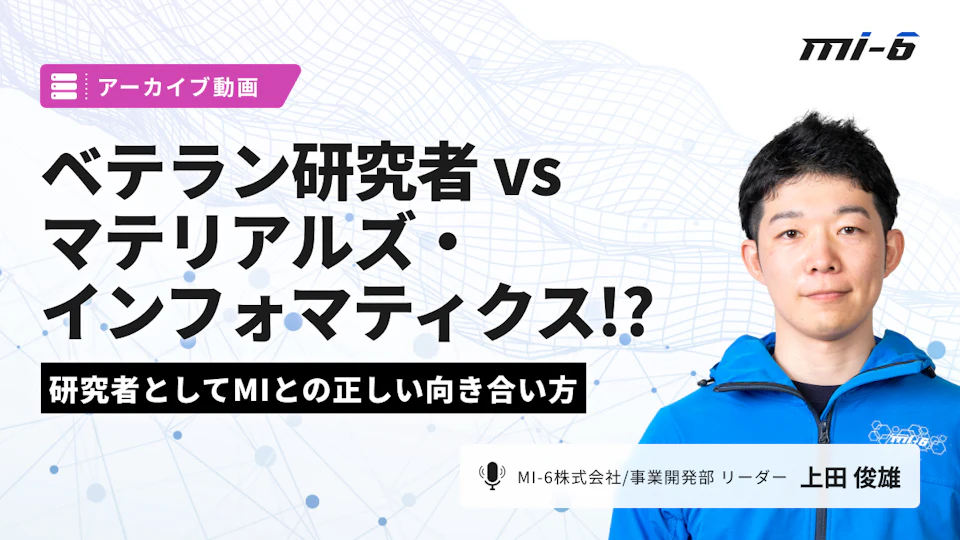セミナー概要
MIを始めるにあたって、実験 vs AIのような文脈で語られるシチュエーションを目にすることもあります。MIに初めて取り組む方によくいただく質問やよく抱かれる誤解として、MIが普及すれば研究者はAIに言われたことをやるだけになるのか、MIをやるにはPythonのコーディングが必須なのか、MIに対して特に実験研究者はどう向き合えばいいのかなど研究者のMIへの向き合い方について疑問をお持ちの方も意外と多くいらっしゃるのではないかと感じています。
本ウェビナーではそういったご質問に答えるべく、実際に実験研究者とMIのアプローチをそれぞれ比較したり、組み合わせて使った場合にどのようなアプローチが最も優れた研究成果に繋がりそうなのかについて検証をした論文をベースに、実験者としてのMIへの向き合い方についてご紹介していきます。
本動画は、2024年4月24日に開催されたセミナー「ベテラン研究者 vs マテリアルズ・インフォマティクス!?~ 研究者としてMIとの正しい向き合い方」の録画動画となります。
コンテンツ
- MI vs 実験研究者? どの組み合わせが最も研究成果が期待できるのか。
- 研究者としてのMIへの向き合い方
- 研究領域での材料ドメイン知識をMIで活かす方法
登壇者

上田 俊雄
Toshio Ueda
MI-6株式会社事業開発部
大阪府立大学工学研究科修了。大学院では有機EL向け材料開発およびデバイス試作を研究。経営学修士(MBA)。
住友化学株式会社にてディスプレイ材料の材料開発およびMIを用いた開発に従事し、2019年より現職。 現職では事業開発として多くの会社のMI活用をサポートしている。
対象者
- MIにこれから初めて取り組む方
- 実験研究者でMIについての向き合い方を考えている方
- マネージャーや管理職など研究組織内でのMIの導入検討する立場の方
問い合わせ先
MI-6株式会社 事業開発部:bd@mi-6.co.jp
※お申し込みいただくと視聴ページへ遷移いたします。もし、視聴できない場合はお手数ですが、問い合わせ先のメールアドレスへご連絡ください。また迷惑メールの設定や、メールアドレス記載の誤りによって、視聴ができないケースがございます。 設定確認と登録アドレスに間違いがないよう、ご確認をお願いいたします。
※同業他社企業のお申し込みはお断りしております。